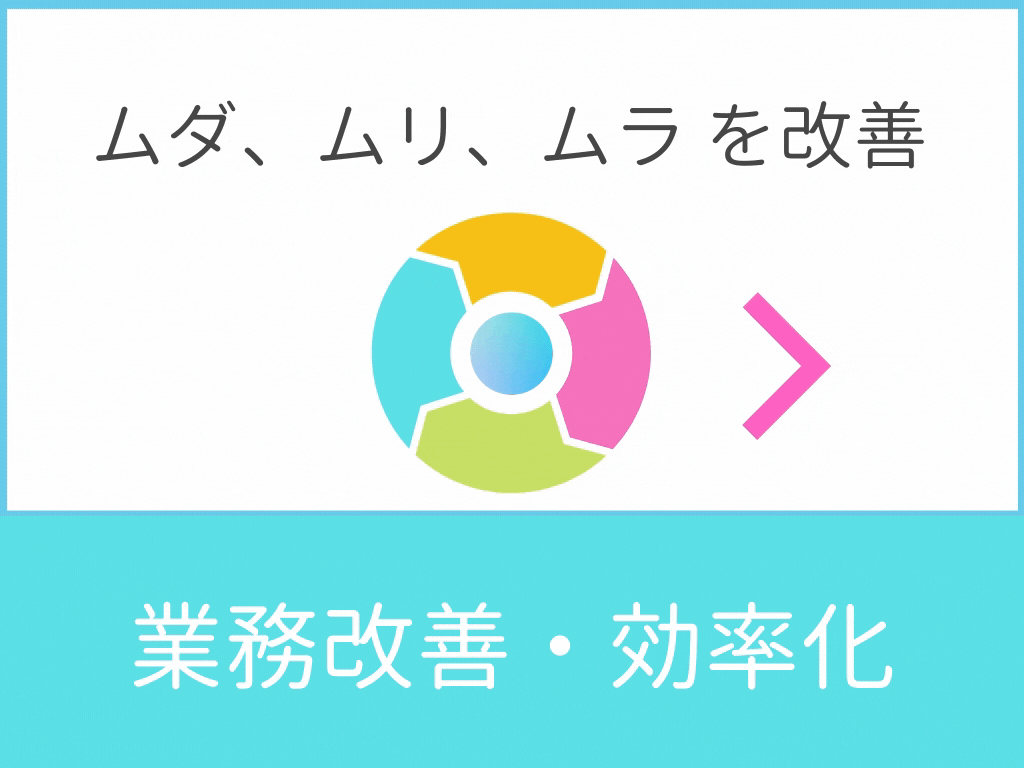改善効果を数値化して、恣意性のない公正で客観的な基準で評価する
【業務改善|第3回】
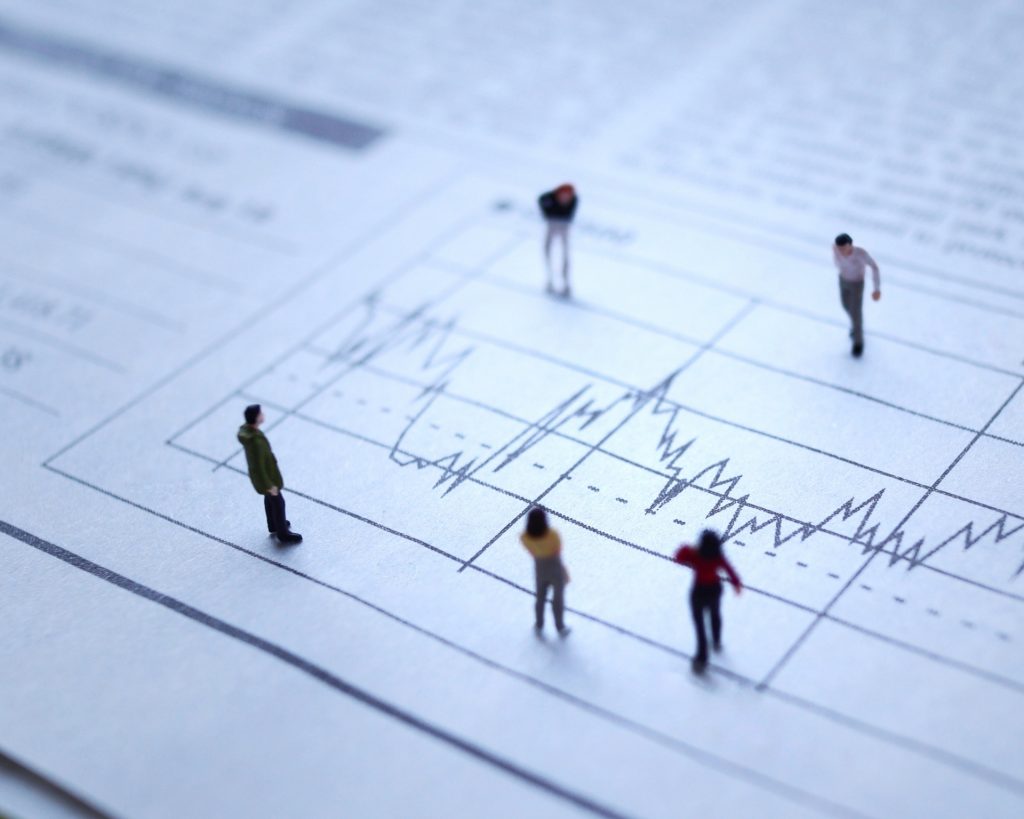
現状分析にエネルギーを使い過ぎて、改善に取り組めないことが無いように
改善を進めるには、現状を分析することからスタートです。強み、弱みを把握し、現在の経済環境、会社方針などを踏まえて、実際に取り組む改善テーマを決定するのが一般的な流れとされています。
ただ、実際の現場では、現状分析でエネルギーを使い果たし改善に入れないケース、改善の取り組みが最後まで終わらないケースなどが散見されます。当初の期待効果を得られず、道半ばで終わってしまっては、まったく意味がありません。
現状分析は必須ではあるものの、身近な問題、課題を改善することが、一番分かり易いアプローチであると言われています。小さな実績の積み重ねが、結果的に大きな効果を得ることになり、担当者の自信を醸成することにも繋がります。
まずは身近な課題から、改善に取り組んでみてはいかがでしょうか?

「不…(不のつく言葉)」を思ったら、それを改善の対象に
世の中、「不」がつく言葉は多くあります。
「不」は、名詞または形容動詞の語幹を打ち消し、否定する役割を担っています。
■ 不 がつく言葉
- 不足
- 不要
- 不正
- 不安定
- 不衛生
- 不快感 など
仕事、業務、順序、考え方など、日常で「不…」と感じることがあれば、そこに改善の余地があるということです。気が付いたら小さなことでもすぐに取り組む、これが現場で改善を進める際の大切なポイントです。
身近に、不毛だな…と感じることはありませんか?
改善は4種類のアクションで

取り組むテーマが決まったら、具体的なアクションに入ります。業種、業態、会社規模に関係なく、4種類のアクションの中から最適なものを選択して、掛け合わせて取り組むことになります。
■ 4種類の改善アクション
- 排除|作業、業務の目的、納得できる正当な理由がなければ排除する
- 結合/分離|個々で取り組んでいる類似の作業、業務を結合し、集中化する
- 交換/代替|作業、業務の順序、場所、担当者を入れ替える
- 簡素化|作業、動作、工程のあるべき姿をイメージして、何か一つを簡素化する
一番効果が大きい取り組みは、排除です。
改善に取り組むにあたり、まず排除を取り組めるか否かを検討することから始めましょう。
改善を通じて、仕事の価値を向上させる
改善はコスト削減、コスト管理のためと思われがちですが、コスト削減で本当に利益は生まれるのでしょうか?
- 価格が安くても、一定の機能とデザインが備わっていなければ売れない…
- さまざまな機能、先進的なデザインが備わっていても、価格が高すぎては売れない…
大切なのは、お客様が求めているニーズを汲み、顧客満足が得られる価格で提供することです。お客様のニーズを反映した上で、商品、サービスの価値を高めるための改善を継続して行う姿勢が重要です。

尚、仕事の価値を向上させるには、インプット(経営資源)とアウトプット(売上、品質、納期など)を両輪で考えていく必要があります。インプット「1」に対して、アウトプットは「1」以上でなければ、新たな価値は生み出せていないことになります。
- インプットを改善するか?
- アウトプットを改善するか?
でき上がりの結果(価値)が上積みされるアクションを取りましょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
改善効果の数値化は必須!恣意性を排除して、公正で客観的な評価を

自社の商材を言い値で売ることができれば、コスト管理は不要です。欲しい利益をベースに、販売価格を設定することができるからです。
但し、需要には上限があり、価格は市場原理で決定されます。厳しい競争環境をどうすれば生き残ることができるのかを考えて、実践していかなければなりません。
企業活動はコストとして計上されることを考えると、すべての活動を数字に換算することは可能です。故に、自社でコントロール可能な数値は「コスト」です。確実に利益を出すためには、コスト管理の徹底は必須と言えるでしょう。
改善効果の達成度、評価を図る手段として金額で比較することが最も分かり易く公平性を有しています。改善を進める際には、すべてのアクションを必ず数値化して取り組むようにしましょう。
【アーカイブ|業務改善】
- 1|業務改善のポイントを、コンサルタントの視点でお伝えします
- 2|改善は競争力を伸ばす!成長、成功、拡大に改善を活用する
- 4|品質の向上、動作の効率化、作業のスピードアップは、改善の継続により効果が表れる
■ ビズハウスの業務改善研修はこちら