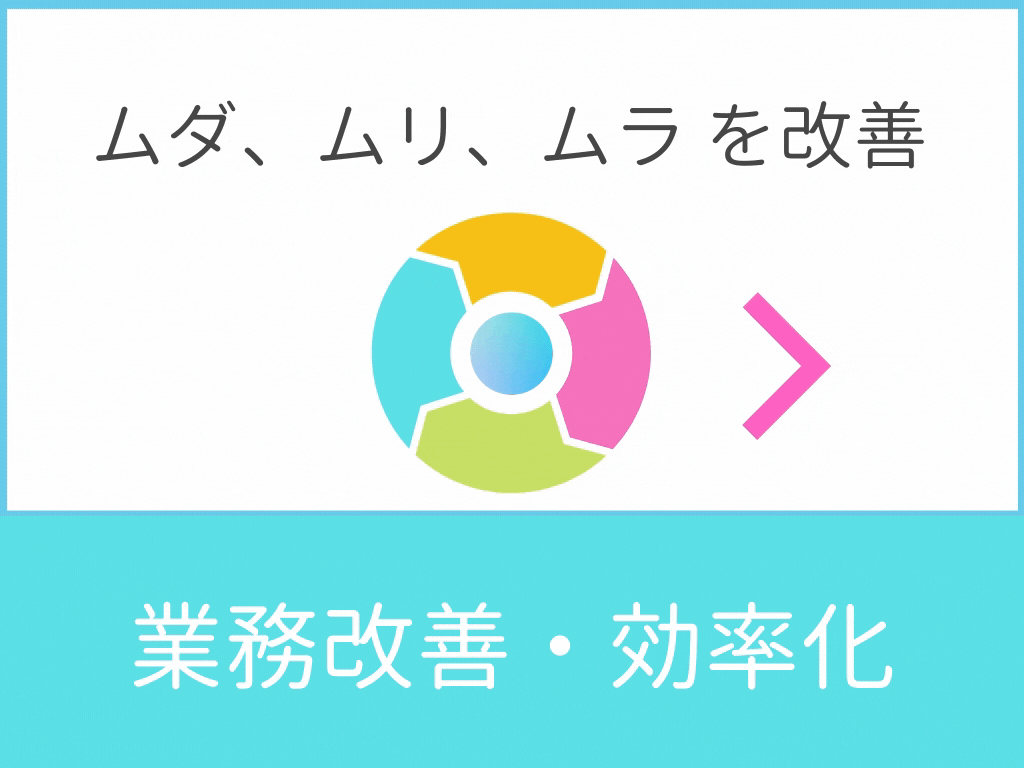改善活動は競争力を向上させる手段!成長、成功に改善を活用する
【業務改善|第2回】

自社の持つ競争力の根源とは
- 自社の競争力の根源とは何ですか?
- 自社の競争力を維持するには、何が必要ですか?
改善を進める前に、自社の強み、弱みとは何かを分析する作業は必須です。その分析結果を踏まえて、強みを伸ばす改善か、弱みを補完する改善か、改善の方向性を決定することになるからです。
さまざまな「力」の中で、自社の持つ競争力の根源とは何か、改めて考えてみましょう。
■ 会社の力とは!?
- 設計力
- 生産力
- 技術力
- 資金力
- 人材力 など
競争力の向上は、イノベーション、メンテナンスと改善の合わせ技で
力を強化する、創造する手段は改善だけではありません。他にもイノベーションやメンテナンスがあり、業種、業界、社員の特性によって、どのアプローチが適切かを考える必要があります。
リーダーは、限りある経営資源を効率的に活用して、会社を強くしていくことが求められます。
どのような手段が最適か、どのようなテーマに取り組むべきか、周囲とコミュニケーションを取りながら、判断するようにしましょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
日本と欧米・欧州の違い

会社を強くしたい、成長させたい気持ちは古今東西同じですが、日本と欧米、欧州を比較してみると、その行動アプローチは異なります。
■ 日本企業(日本人)の場合
標準、平均、枠組みを作ってそれを維持する、守る、直す、良くすることを得意としています。そのため、改善を手段として取り入れるケースが多くなっています。
■ 欧米企業(欧米人)の場合
新しいものを生み出す力に長けており、イノベーションを手段として成長、拡大を図るケースが多くなっています。ここ数年でも、テスラ、グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンなど、革新的な商品、サービスが次々と出てきているのが何よりの証拠です。
ここでお伝えしたいのは、改善とイノベーション、どちらが良いか悪いかという話ではありません。国民性の違いがそのままアプローチの違いに反映されている、という事実です。
それぞれが得意とするアプローチで、十分に勝負することができます。不得手なアプローチでエネルギーを浪費することが無いように、自社に合ったアプローチをぜひ見つけてください。
改善の目的、意義、意味を考える
- なぜ、改善しなければいけないのか?
- なぜ、改善に時間とエネルギーをかけて取り組む必要があるのか?
これらの理解と共有がなされなければ、目標とする効果を得ることは難しいでしょう。
改善の狙いは、仕事の価値を高めることです。
変化に対応できた、コストを削減できた、スキルが向上した、モチベーションが向上したなどの効果は、あくまで二次的な効果です。改善を通じて仕事の価値を高めることこそ、改善に取り組む真の理由ではないでしょうか。
■ ビズハウスの業務改善研修はこちら
改善するテーマを見つけよう!
組織が大きくなればなるほど、ムダなこと、ムリなこと、ムダとムリが混在したムラなことが存在しています。誰が見ても明らかに改善が必要な事案はさておき、自分は改善が必要だと思っても、相手が必要だと思っていなければ、思うように進めることはできません。
立場、部署、仕事の内容が違えば、物事の見方も変わります。そんな時、どうすればいいのでしょうか?
■ 改善に取り組む際の準備とステップ
- 改善を評価する仕組みを整備する
- 初めは重くないテーマから取り組む
- 徐々に質、量が伴うテーマへシフトする
- 協力が得られない部署、人を積極的に巻き込む
- 定量的に効果が測れるよう、測定方法や基準となる指標を設定する など
改善は会社として推奨している取り組みであり、効果が得られれば相応に評価することが周知されれば、一致団結して取り組む気運は自然と醸成されます。
改善を積極的に取り組めるような環境を整備することも、とても大切な取り組みです。
【アーカイブ|業務改善】
- 1|業務改善のポイントを、コンサルタントの視点でお伝えします
- 3|改善効果を数値化して、恣意性のない客観的な基準で評価する
- 4|品質の向上、動作の効率化、作業のスピードアップは、改善の継続により効果が表れる