自分を責めず、自分に優しく!働き方や職場環境の改善&最適化を継続して、モチベーションを上向きに
【研修ライブ|第8回】

モチベーション低下の原因はさまざま!原因を究明して、解決策の実行は継続的に
職場を取り巻く環境は、日々変化します。追い風か逆風か、さまざまな局面に適宜適切に対応しなければならないビジネスパーソンは、多くのストレスを抱えながら業務に励んでいるのではないでしょうか。
人間は、感情を持った生き物です。それゆえ、心身のコンディションの浮き沈みは必ず起こるものです。
そのことを前提に、どのようにしてモチベーションの低下を抑えるか、モチベーションの向上に繋げていくかを考えて、職場風土の改善や雇用条件の見直しなどを進めていかなければなりません。
■ モチベーション低下の悪循環から抜け出すために…
- 相手を責め過ぎない
- アメとムチ、アメばかりにならないように
- 気合と根性による解決(内的要因)ではなく、外的要因にも目を向ける
会社としてやるべきこと、一人ひとりがやるべきことを整理して、働きやすい環境作りを継続的に取り組めるように。
各自が協調と協働の意識を高めていく必要があるでしょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
仕事のスタートを挫く、モチベーションを損ねる指示にならないよう要注意!
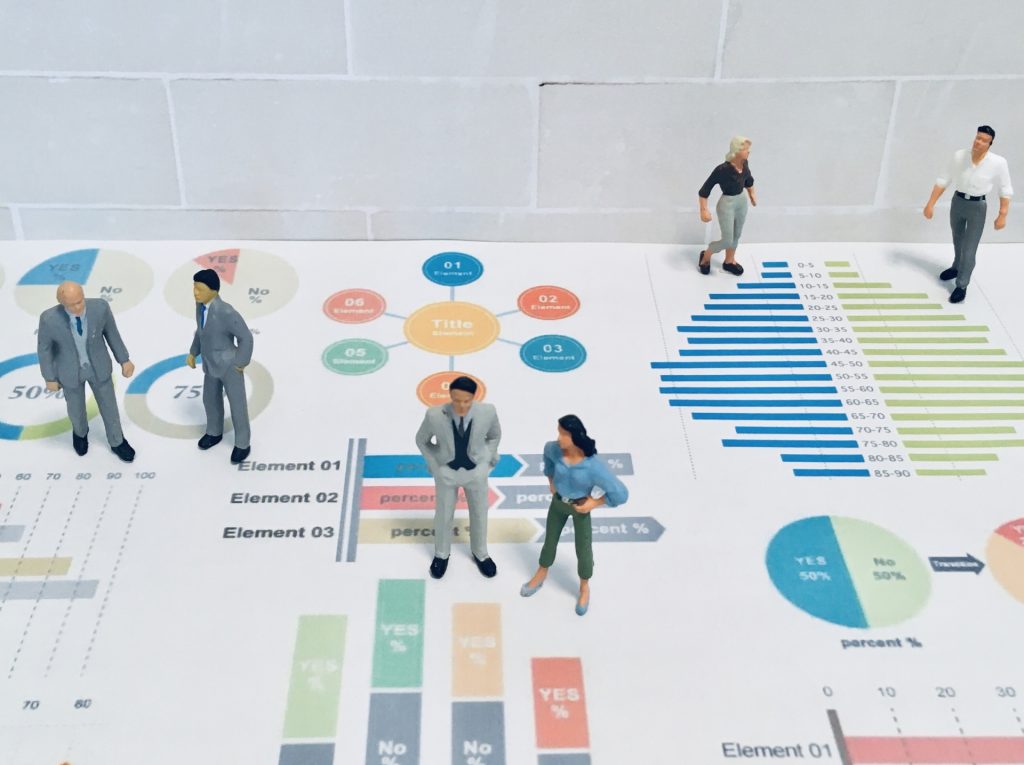
日常のどのような仕事であっても、社内外の方々から相談、依頼、指示があってからスタートです。最初の伝え方や内容に留意して、相手のモチベーションを喚起する工夫が求められます。
言い方を変えれば、最初の伝え方で躓いてしまうと、後々に悪影響を及ぼしかねません。
発信側と受信側で認識の共有ができず、ボタンのかけ違いが起こらないように、それぞれが適切に対処していく必要があります。
■ 相手のやる気を奪う原因
- 曖昧
- 一方的
- 後出し
- 朝令暮改
- 適正無視
まず初めにできることは、発信側が伝えたい内容を5W3Hで整理して伝達することです。情報の抜け漏れを無くすだけでも、かけ違いを減らすことができるでしょう。
特に、仕事の目的や意義(WHY)は必ず伝えるように。また、期待や懸念も包み隠さず伝えることで、相手との距離をぐっと縮めることができるでしょう。
一方の受信側は、しっかりと「きく姿勢」を取ることが重要です。不確かなことや不明瞭なことなど、理解できなかった部分は改めて確認する行動が、ズレや思い込みの解消へと繋がります。
アメとムチには限界があり!相手の心理状態に合わせて、意欲喚起のアプローチを変えられるように

- 仕事が成功すれば、報酬アップ!
- 仕事が失敗すれば、報酬カット…
インセンティブの大きさを組織マネジメントに活用する会社は増えていますが、果たして上手く機能しているのでしょうか?!
常に業績に対するプレッシャーにさらされ、過度に競争が促される環境では、同僚との協調性は損なわれてしまいます。目標達成ばかりが注目され、必要最低限の行動しか取らなくなり、結果、働きづらい職場に…
大きな報酬を夢見て一時的にモチベーションは喚起されるかもしれませんが、嫉妬や敵意が渦巻く環境に身を置くことで、大多数の方々が疲弊してしまうのが一般的です。
報酬を得る、罪を避けるために生じるモチベーションのことを、外発的動機付けと言います。
「・・・をしたら、・・・を貰える」という交換条件付きの報酬(外発的動機付け)は、「報酬を貰うために仕事を行う」と置き換わり、内発的な興味や自律性を失わせてしまいます。
アンダーマイニング効果と呼ばれるもので、モチベーションを高めようとアメを差し出し過ぎると、逆に組織全体のパフォーマンスを低下させてしまう現象を起こしてしまいます。

モチベーションには、種類があります。相手の心理状態に合わせて、意欲喚起のアプローチを変えましょう。
■ 働くモチベーションの4段階
- 働く気なし
- 仕方なく働く
- 大切に働く
- 楽しく働く
「働く気なしの状態から仕方なく働く状態」まで引き上げるには、報酬、罰、義務感を刺激すると効果的とされています。頑張りを適切に評価する仕組み、取り組みが不十分なときに被るデメリットなどを開示しておくと良いでしょう。
「仕方なく働く状態から大切に働く状態」まで引き上げるには、仕事の意義と自身の目標が重なるアプローチが効果的とされています。また、「大切に働く状態から楽しく働く状態」に引き上げるには、仕事で達成感や喜びを得られる機会をもたせることが重要です。
自分の力を発揮して、仕事を通じて社会にどれだけ貢献できたか。その繋がりや成果を実感できるようになったときに、仕事の楽しさを感じられるようになるのではないでしょうか。
■ 仕事でモチベーションが喚起される場面
- 難易度の高い業務を任せてもらう
- 新しい知識やノウハウが得られる
- 意見や考えを自由に表現できる
- 権限や裁量の範囲が広がる など
目先の成果を重視し過ぎてしてしまうと、失敗を恐れて困難な挑戦は避ける風土に。また、数字に表れない裏方仕事やプロセスを軽視してしまうと、組織の弱体化に繋がります。
成果主義やインセンティブの導入はあくまで不満足要因(無ければ不満に繋がる)であって、決して満足要因(あれば満足感に繋がる)にはないことを忘れないようにしましょう。