心理的安全性が注目される理由とは?!多様化が進むビジネス環境において、心理的安全性の重要性が高まっています
【心理的安全性|第1回】
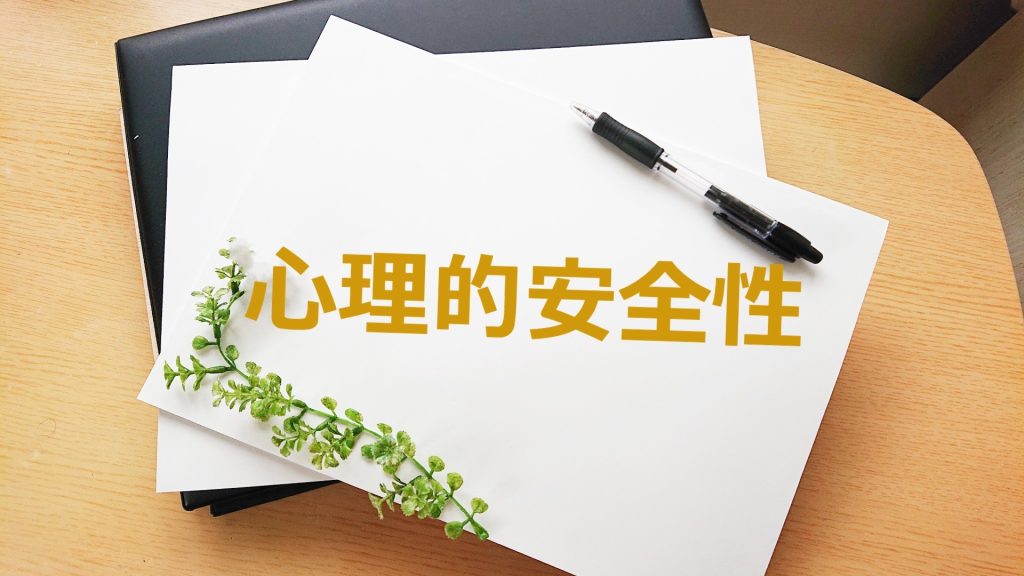
不確かなビジネス環境で生き抜くことができるように!心理的安全性の重要性が高まっています
昨今のビジネス環境は、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の高まりによって、将来の予測が難しい状況に置かれています。変化に対応できる柔軟性、グローバル化による多様性を受け入れながら、より高度な付加価値を創り出すことが求められています。
そのため、ビジネスパーソンの個性や特徴を最大限発揮できるよう、会社が上手にマネジメントしていかなければなりません。これまでのトップダウン型経営ではなく、現場の意見を尊重するボトムアップ型経営の方が、時代にマッチしている印象です。
昨今注目されている心理的安全性とは、「誰もが気兼ねなく自分の意見を発言でき、相手と話し合える状態にあるという確信を全員で共有している状態」を意味します。
そのメリットは大きく、心理的安全性の高い職場づくりに取り組む企業が増えてきました。言い方を変えれば、パフォーマンスの最大化やコミュニケーションの活性化を図るには、心理的安全性は必要不可欠となりました。
■ 心理的安全性が高い職場のリターン
- 生産性、パフォーマンスの向上
- 業務改善、イノベーションの促進
- 意見交換、コミュニケーションの活性化
- 信頼関係の構築、チームワークやエンゲージメントの向上 など
■ 心理的安全性が低い職場のリスク
- 離職者の増加
- ミスやトラブルの増加
- 問題の隠蔽、不正の増加
- コミュニケーションに消極的、否定的な評価への不安 など
ビジネスパーソンは、さまざまな局面でストレスを感じながら業務に励んでいます。それゆえに、人間関係が円満で心穏やかにいられる職場、意欲と活気に満ち溢れたチームで働くことができれば、より大きな成果を実現することができるでしょう。
仲間と意見を出し合いながら環境を整える取り組みは、自分達の組織や職場を将来にわたって成長させる重要なポイントです。
社会心理学や組織行動学に基づく心理的安全性を正しく理解して、職場を自律的、創造的に変革していきましょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
成功する組織やチームにあるものとは?!心理的安全性に繋がる7つの習慣を実践する

Googleは2012年から2016年までの4年間、生産性の高いチームをつくる方法を見つけることを目的として調査、研究を行いました。
「プロジェクト・アリストテレス」と呼ばれる同取り組みは、Googleの自社サイト「re:Work」において、成果を出し続けている企業、組織、チームに共通する要因は5つある(5つの因子)と発表しました。
■ 成果に繋がる5つの因子
- 心理的安全性 誰もが安心してリスクを冒し、意見を述べ、自分の弱さもさらけ出すことができる
- 構造と明確さ 目標、役割、実行計画という3つの要素が明確になっている
- 意味と意義 チームメンバー全員が、自分にとってこの仕事は意味があると実感している
- 信頼性 自分が仕事をしている間に、他のメンバーも質の高い仕事を時間内に仕上げてくれる
- 効果 チームメンバー全員が、この仕事は意義があり、より大きな変化を生むものと確信している
また、5つの因子のうち、組織の生産性や個人のパフォーマンスを高める最大の要因は心理的安全性にある、と結論付けました。
これは、成果を出し続けるには、他者への心遣いや同情、配慮や共感が最も重要であるという意味です。当該プロジェクトによって、働きやすい職場とは心理的安全性が高い職場である、という一つの解が導き出されたのです。
尚、心理的安全性は、チームメンバー全員で作り上げていくものであるため、各自がどのような思考で行動するかがポイントになります。
ビジネスパーソンとして7つの習慣を意識して、自発的に意見を出し合える環境を整えていきましょう。
■ 身につけたい7つの習慣
- 励ます
- 傾聴する
- 支援する
- 尊敬する
- 信頼する
- 受容する
- 交渉する
心理的安全性には4つのメリット! 状況の変化に対して、柔軟に、臨機応変に対応できるように

不確かな時代を生き抜くには、変化を恐れずに、挑戦を続ける姿勢が大切です。心理的安全性を備えた組織やチームは、メンバー全員で物事に対処する基盤が出来上がっているため、その時々の最適なアウトプットを創り出すことができます。
具体的には、心理的安全性によって、4つのメリットを享受することができます。
■ 意思決定
現場に近いメンバーが積極的に発言や提案ができる、心理的安全性の高い組織では、タイムリーで有益な情報共有により、迅速な意思決定が可能に。
■ リスク回避
目標やノルマのプレッシャーが大きい組織では、できないという事実を伝えることができずに、隠蔽や改竄などの不正に繋がる可能性があります。心理的安全性の高い場合には、不正やトラブルが表面化しやすくなり、迅速な対応が可能に。
■ 多様化
創造性、革新性が求められる昨今、価値観の多様化を受け入れて、アウトプットを創り出すことが求められています。画一的な価値観や旧来の考え方をそのまま踏襲せず、アイデアやイノベーションが生まれやすい状態に。
■ 成長性
価値あるアウトプットを創り出すには、失敗は付き物です。挑戦と失敗を恐れない成長する組織、学習する組織に。

尚、職場の心理的安全性を定量化して把握するための「7つの質問」があります。
職場の実態を見える化して、改善活動のきっかけにしていきましょう。
■ 心理的安全性を測定する7つの質問
- ミスをすると、非難される?
- 安心してリスクを取ることができる?
- メンバー間で課題や問題点を指摘し合える?
- 努力を妨害するような行動を故意にする人はいない?
- 働くときにはスキルと才能が尊重され、活かされている?
- 自分とは違うことを理由に、他者を拒絶することがある?
- 他のメンバーに助けを求めることは難しい?
心理的安全性に対する誤解やハードルを取り除き、建設的な対立をいとわず、率直な発言を促す

心理的安全性を高めるには、それを妨げる要因や誤解を特定して解決しなければなりません。人間の感情を上手にコントロールして、心理的安全性への各自の理解を深めていく必要があります。
心理的安全性を妨げる主な要因として、4つの対人リスク(不安)が挙げられています。
- 無理だと思われる不安
- 無能だと思われる不安
- ネガティブだと思われる不安
- 邪魔をする人だと思われる不安
職場において、疑問、懸念、質問、失敗、問題、支援などの報連相や依頼をすると、相手からどのように思われるか不安に駆られてしまう人は多いのではないでしょうか。
組織やチームに対して自分の考えや意見を言葉に表すことを、ヴォイシングと言います。本来であればヴォイシングは評価され、心理的安全性の構築に資する行動ですが、既得権者からすると、既得権を脅かす行為と捉えられてしまうリスクがあります。
そのため、当該リスクを回避するべく、組織のトップやリーダーが率先して発言しやすい雰囲気や環境をつくっていく必要があります。
但し、何でも発言できる環境を整えることが心理的安全性である、という訳ではありません。肩書に関係なく、建設的な対立をいとわずに率直に発言できる環境が、心理的安全性が高い状況であると言えます。
自分の意見や考えを相手に対して率直に伝えても、対人関係が悪くなる心配をしなくていい、という信念が組織全体に共有されている状況が、理想の状況です。
■ 心理的安全性に対する誤解
- 好き勝手にできるヌルい職場、という誤解
- アットホームな職場、という誤解
- 信頼関係を築く、という誤解
- 外交的になる、という誤解