PDCAを上手に回す!知っておくべきCHECK(評価)とACTION (処置是正)のポイント
【PDCA|第3回】
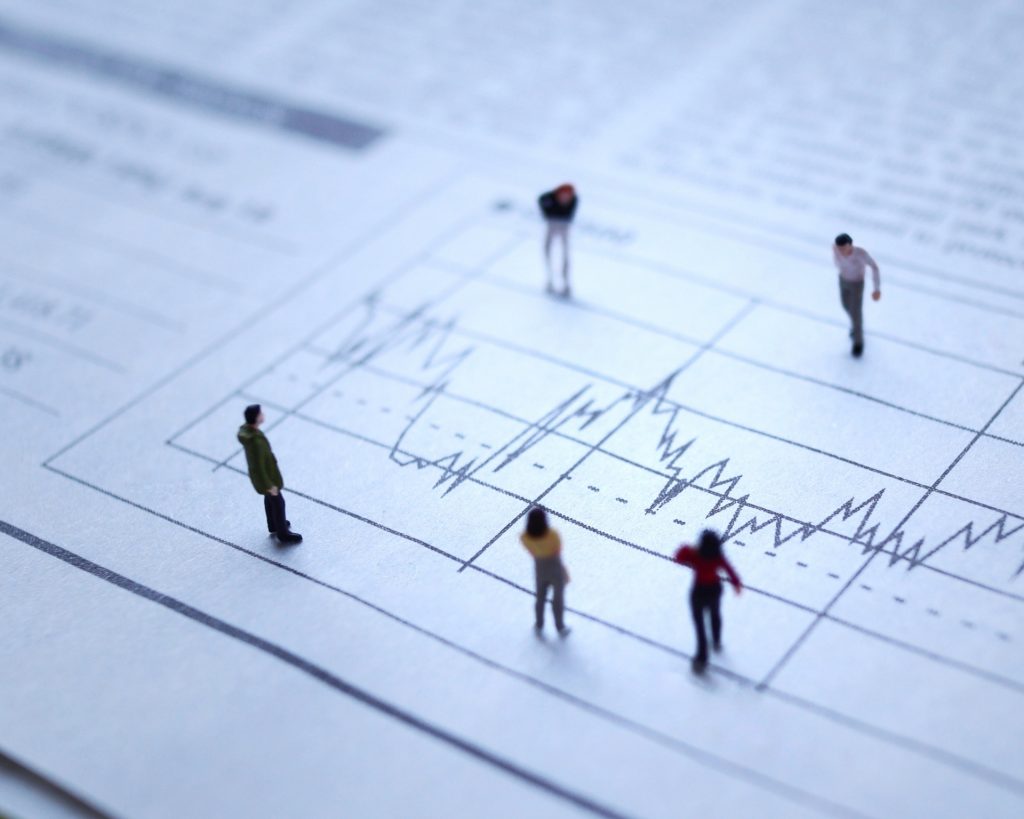
コントロールが可能な評価指標を設定する
PDCAのDOの次は、実行した結果をCHECK(評価)するステップに入ります。
評価の基準、指標のことをKPI(KEY PERFORMANCE INDICATORS)といい、PDCAを設計する際には必ず設定する必要があります。KPIは2種類に分類されますが、PDCAでは行動KPIを設定するのが一般的です。
■ 行動KPI
- 行動の原因、行動の質、行動の量に対しての基準
- 結果を出すために仕掛けた行動が、計画通りに実行できたかを評価
- 結果に至る自身の行動に焦点を当てた指標で、自身によるコントロールが可能
■ 結果KPI
- 結果に焦点を当てた指標で、自身によるコントロールは不可能
- 自分以外の外的要因による影響も含めて、最終的な結果のみで評価
- 結果を出すための途中過程は問わず、目標である基準、指標を達成できたかを評価

結果KPIを指標にして評価を進めた場合、成功、失敗、どちらであっても外的要因による影響を少なからず受けているため、その結果に至った原因を絞ることができません。
失敗の原因を外的要因にしてしまうと、今後の改善に繋げられず、せっかくの変化の機会を失ってしまいます。
- 天気が悪かったから…
- 円安、円高になったから…
- 競合がセールを開催したから… など
言い換えれば、成功したら自身の評価とし、失敗したら外部環境のせいにしてしまう、甘さが生まれてしまいます。
そうはならないように、結果より「結果に至る行動」に焦点を当て、自責で物事を考え、反省できる行動KPIを設定するようにしましょう。
成果に直結する重要な要素を見極めて、そこに繋がる行動KPIを設定する
行動KPIは、目標達成に直結する指標を設定できるかがポイントです。
■ 評価指標設定のプロセス
- 目標を要素分解する
- 分解した要素を重要度、緊急度の2軸で分類し、優先順位を見極める
- 優先順位の高い、自身でコントロール可能な指標を数字で設定する
以下、ケーススタディとして、売上高アップに繋がる行動KPIを設定してみましょう。
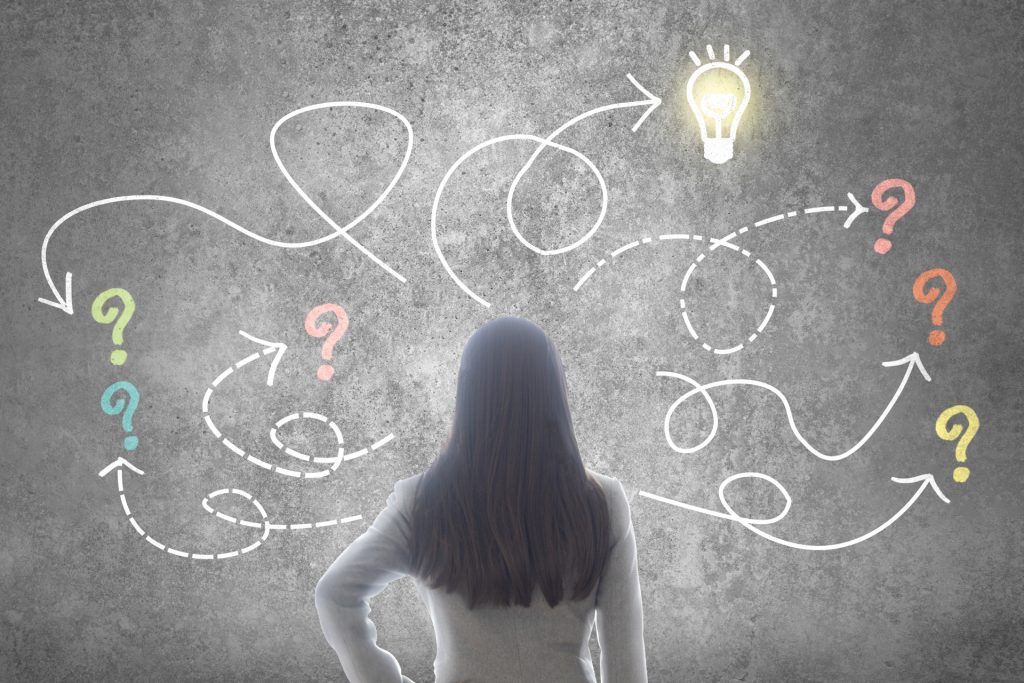
■ 目標を要素分解する
売上高は、細かく要素分解することができます。
- 単価×数量
- 市場規模×市場シェア
- 地域、商品、事業等のセグメント など
例えば、「単価×数量」は「客単価×客数」「販売単価×販売数量」「一店舗当たりの売上高×店舗数」にて、より細かく分析することが可能です。なるべく数値で測定しやすく、行動に結びつけやすい要素にフォーカスできるかがポイントです。
影響度の大きさ、ブレの大きさより深く検証して、目標達成に必要な要素を見つけましょう。
■ 分解した要素を重要度、緊急度の2軸で分類し、優先順位を見極める
今回は「単価×数量」にフォーカスし、その中の「客単価×客数」で検証を進めていきます。仮に「客数」が「訪問件数×訪問時間」によって大きく数字が動いていることが分かれば、「訪問件数」をKPIと設定することができるでしょう。
注意すべき点は自分でコントロール可能な指標を数字で設定すること、です。行動KPIと定義される指標であれば、どのようなKPIを設定してもOKです。
■ 優先順位の高い、自身でコントロール可能な指標を数字で設定する
- 今までの訪問件数は何件だったか?
- 訪問件数をどれだけ増やせば、どの程度成果に繋がるのか?
仮説を立てて、できる限り数字で見える化しましょう。KPIは、部署、業務、プロジェクトごとに設定することが可能です。
第三者が見ても納得感があり、評価する側、評価される側にとって公平性のあるKPIの設定が求められます。
プロセスを定量化して客観性、公平性、妥当性を持たせる
各業務の代表的なKPIをご紹介します。
■ 営業
- 訪問件数
- 見積作成時間
- 新商材の更新回数 など
■ 人事
- 研修実施件数
- 1on1カウンセリング件数
- 健康診断実施率 など
■ 購買
- 相見積もり実施件数
- 仕入業者の開拓件数
- 調達期間の短縮時間 など
■ 品質
- 検査工程の工数
- 検査チェック件数
- アイドリング実施時間 など
自社の論理を相手に押し付けるのではなく、お客さまが真に喜ぶことは何かを考えてみましょう。
お客さまからの期待、お客さまとの約束と連動する指標を設定することができれば、将来の成果に繋がる可能性は高まるでしょう。
上手くいったことは仕組化し、上手くいかなかったことは処置是正を

- お客さまとの約束は果たせたか?
- 自社にとって利益に繋がる結果となったか?
その分析と評価に基づいて、PDCAの2週目に繋げるために処置是正(ACTION)を行います。特に、問題点への対応は、メンバー全員で原因を究明し、早急に解決しなければなりません。
一方、上手くいった事例は、組織全体で共有し、仕組み化(STANDARD)することをお勧めします。
成功事例をマニュアルにまとめてルーティンで回すことができれば、組織力の底上げにも繋がります。仕組み化は、組織の効率化を図る上で、とても有意義な取り組みと言えるでしょう。
PDCAの開始から結果が出るまでには、相応の期間とエネルギーが必要です。成功へのこだわり、達成への覚悟が成否を分けると言っても過言ではありません。
協働意識を醸成して、能動的、積極的に取り組み、成功事例を仕組み化していきましょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
PDCAを上手に回して、日常のマネジメントに最大限活用する

PDCAは、現場マネジメントの手段として広く活用されています。しかしながら、PDCAを回すのはそう簡単ではなく、期待通りに人が動かない限り、成果を上げることはできません。
- 当たり前のことを、当たり前にやる
- こだわりを持って、しつこく継続する
- 経営者目線、現場目線、そして当事者意識を持つ
ハードとソフト、両面で準備が整えば、後は目標達成に向けて前進するのみ!
失敗を恐れず、トライアンドエラーを繰り返しながら、成功、成長、正解へ繋がる道を切り拓いていきましょう!