戦略的政策形成研修事例 – 北海道市町村職員様への提供内容と成果をご紹介します
【取組実績|第38回】

戦略的政策形成研修のカリキュラム、研修の雰囲気などをご紹介します
北海道内の自治体で働かれている20代から50代の職員の方々を対象に、戦略的政策形成研修(2日間コース)を実施しました。
毎年恒例、今回で3回目になる本研修は、前回から名称を変更し、最新の情報やトレンドなどを盛り込んだ内容でご提供しました。
尚、本研修の実施に際して、目標に据えた内容は3つあります。
- 現状を踏まえて、どのような将来像を描くのか、考え方やフレームワークをインプットする
- 自由で柔軟な発想をもとに、今後の街づくりに対する自らの想いをアウトプットする
- 道内で働く同世代の職員とコミュニケーションを図る機会にする
今回も一方的な講義にならないよう、研修の半分を講義に、残りの半分はディスカッションやグループワークを多用するなど、双方向でコミュニケーションが生じるよう配慮したカリキュラムを設計しました。
■ 戦略的政策形成研修カリキュラム
一日目
- 地方自治体を取り巻く環境
- 情報の活かし方
- 現状を分析する
- 将来を設計する、行動を計画する
二日目
- 価値を創造する、提供する
- 政策形成シート発表
PEST分析、SWOT分析、7つの資源などのフレームワークを使った現状分析、言葉と数字による将来設計、6W3Hによる行動計画など、新しい知識やノウハウをインプットいただけたと思います。
また、地方自治体の存在意義、コアコンピタンスの位置付け、今後のご自身のキャリアを考える機会になったと思います。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
オンリーワンの街づくりを!自由に柔軟な発想で、将来のあるべき姿や存在意義を考える
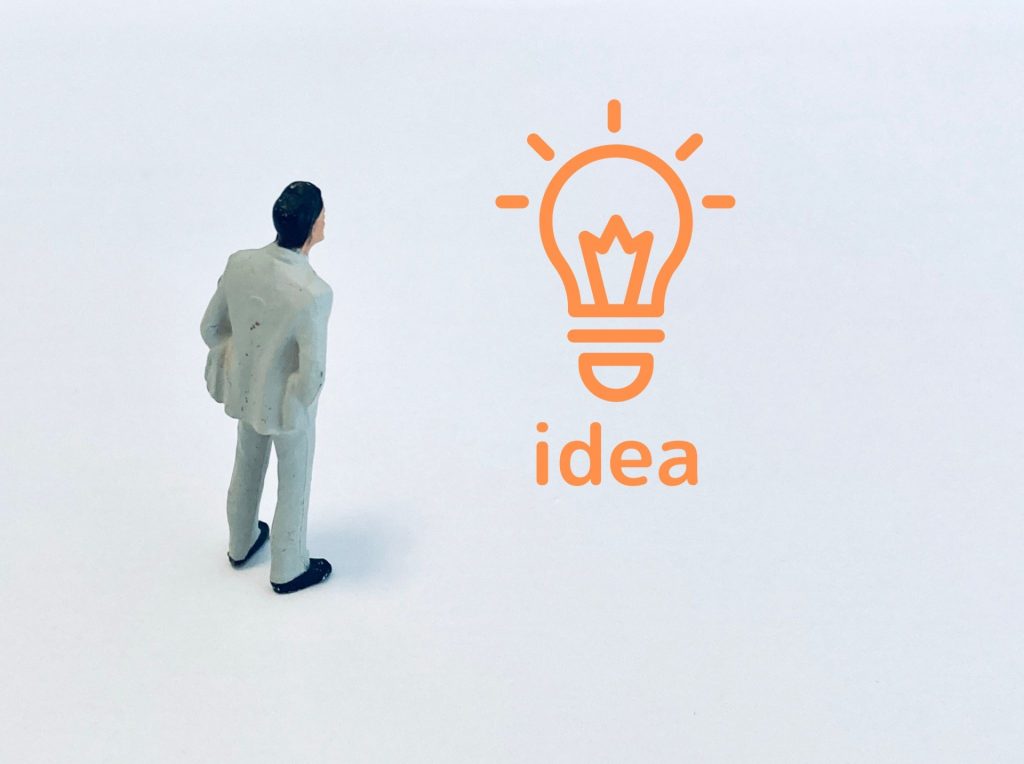
今回も本研修のインプットを踏まえて、政策形成シートを作成いただきました。今後の街づくりをどのように推進していくか、現状分析、将来設計、行動計画と順番に取り組んでいただき、研修二日目に発表いただきました。
各自治体で置かれている環境、それぞれが持つコアコンピタンスは異なります。強みを生かす街づくりか、弱みを補う街づくりか、ご自身が目指したい「街の将来」を真剣に考えていただけたと思います。
以下、今回提出いただいた政策形成シートの中で印象的なテーマをご紹介します。
■ 近未来農林水産都市
- 日本の食を支える地域として、近未来の先進的な農業技術をいち早く取り入れて進化する街に
- 高規格通信網を整備して、農作業の担い手を、AIを搭載した自動運転機械に100%移行する
- 食物工場により作付面積を増加させて、農作物の収穫量アップ、新たな雇用を創出する
■ 恐竜に会える街
- カムイサウルスジャポニクスの全身骨格の発掘を契機に、恐竜推しの街づくりを推進する
- 新博物館のオープンに合わせて、看板、モニュメント、車両、バスなどを恐竜デザイン一色に
- 国内外の観光客のほか、修学旅行生もターゲットに、観光の受け入れを強化する
■ 自給自足ができる街
- 静かな生活、豊富な農産物に溢れた、豊かさを感じられる街に
- 商工部局による作物のブランド化、広報部局による海外への発信を通じて、街の知名度向上を図る
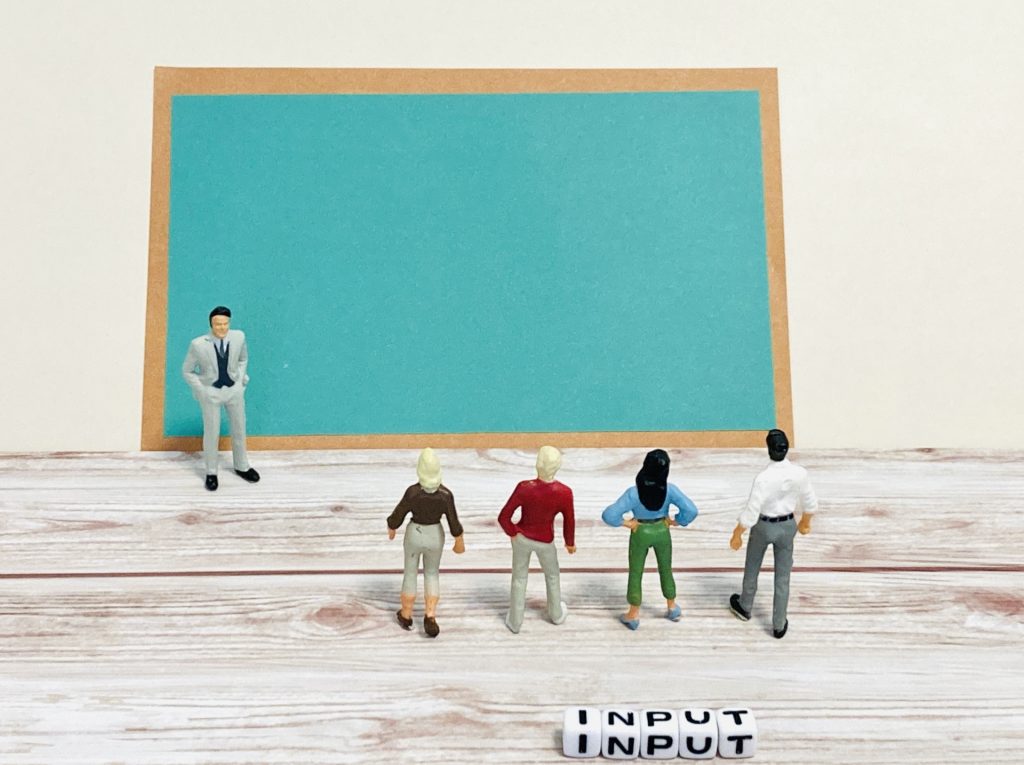
新しいことを想像する、無から有を創り出すには、多くのインプットが基盤になります。街づくりも同様で、地域の特徴を知らなければ、現状を踏まえた街づくりを推進することはできません。
- 日頃からインプットを継続して、今までにはないアウトプットを創り出せるように
- その場所でしか体験できない価値を、地域住民や来訪者へ提供できるように
本研修で学んだことをきっかけに自治体の存在意義を明確にして、他にはない、新しい取り組みを発信し続けてほしいと思います。
クライアント情報│北海道市町村職員様

北海道市町職員
- 対象 北海道岩見沢市、富良野市、恵庭市、月形町、津別町などからの選抜された職員
- 場所 北海道庁別館
各市町村のホームページはこちら
※本研修は、一般社団法人日本経営協会様からのご紹介、ならびにサポートを受けて実施しました