傾聴力を備えたビジネスパーソンを目指す!軋轢が生じてもプラス効果に注目して、コミュニケーションを絶やさないように
【職場づくり|第4回】

傾聴する姿勢を備えているか?!相手の情報、状況、ニーズを引き出してから人間関係の構築を
プレゼンテーションのイロハ、提案力を強化する方法など、情報発信のノウハウを学べる書籍やセミナーが人気を集めています。相手に正確に伝達するスキル、発信する力はビジネスパーソンにとって必要不可欠なものであると思います。
しかしながら、相手が知りたいこと、求めていることと相違する発信を何回行っても、それは相手にとって有意義なものにはなりません。時間は有限であり、相手に効果やメリットを提供できる発信となるように、内容とタイミングは十分に計る必要があります。
- 相手の立場に関係なく、話をしっかりと聞く姿勢、態度はできていますか?
- 相手の情報、状況、要望などを正確に理解するために、質問、相槌などで引き出していますか?
人は誰でも自分の話をしたいことを前提に、職場づくりやコミュニケーションのあり方について考えてみましょう。

職場コミュニケーションに問題があると感じている方は、受信する力の向上、言い換えれば、まずは相手が話していることに耳を傾けることからスタートしてみてはいかがでしょうか?
発信ばかりが注目されますが、受信もコミュニケーションの一環であり、相手を知れるチャンスと捉えることができます。
親身に傾聴する姿勢は相手への興味を示す行為であり、信頼感や安心感を与えます。根掘り葉掘り、問い詰める質問ばかりでは相手は構えてしまうため、いかに話しやすい雰囲気を醸成できるかがポイントです。
話し手が話しやすい環境を醸成して、職場コミュニケーションを活性化、風通しの良い職場づくりに繋げましょう。
相手の話題に合わせて、ボディランゲージ、顔の表情、視線の動きをフル活用して傾聴する
相手から正確な情報や本音を引き出すためには、体全体で傾聴できるようになる必要があります。
傾聴力を備えることで、上司からは「話せる相手」として、後輩からは「相談できる先輩」として、一目置かれた存在になれるでしょう。

■ ボディランゲージで傾聴する
- 相槌を入れる
- 身を乗り出す
- 腕組みをしない など
■ 表情で傾聴する
- 楽しい話は、笑顔で
- 真剣な話は、真面目な表情で
- 悲しい話は、同情的、感情的な表情で など
■ 視線で傾聴する
- 相手の目を見る
- 目線を合わせる
- 視線を泳がせない
- 適度に視線を外す
- よそ見ばかりしない など
相手を心から理解したい、と思う気持ちや態度を見せることは、相手との関係性を構築していく上で大切なことです。また、相手の情報を先にインプットした上で営業、提案、交渉した方が、相手のニーズと齟齬が無く、効率的に物事を進められるのではないでしょうか。
人や情報が集まれば、仕事に好影響を及ぼします。仕事が円滑に進めば、人や情報はより自分の周りに集まります。
発信力と傾聴力、自分にとってどちらが有意義な力になるか、改めて考えてみましょう。
コミュニケーション不足は身近な問題、課題が原因!組織の悪い癖にならないように、すぐに改善を
組織やチームのコミュニケーションが上手くいっていないとき、最新のツールや話題のクラウドサービスを導入しても、期待通りの改善効果が得られることはありません。原因は手段にあるのではなく、他のところにあるからです。
コミュニケーションを改善する近道は、何よりその原因を解決することです。原因を見つけて対処する地道な繰り返しが、社員一人ひとりのモチベーションアップを促し、強い組織、壁の無い職場の形成に繋がります。
役割分担や組織体制が不全化する前に、早めの原因究明と対処に取り組みましょう。
■ コミュニケーション不足の原因
- 会話をしづらい環境
- 話しかけづらい雰囲気
- 常に時間が無い働き方
- 上司、先輩から教わる場がない
- 業務の属人化が進み、助け合わない など

因みに、コミュニケーションの量と質、自分の周りではどちらを充実させる必要がありますか?
「量」を充実させたい場合は、インフラの整備、連絡ルートの明確化、報連相の評価する取り組みを。「質」を充実させたい場合には、連絡フォーマットの整備、6W3Hによる情報整理の徹底など、会社全体で取り組んでみてください。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
コンフリクトの原因は双方に!プラスの効果に注目して、コンフリクトを恐れずに
意見交換やコミュニケーションが活発になればなるほど、主張の食い違い、情報の非対称性による対立や軋轢は必ず生まれます。コンフリクトによるデメリットやマイナス効果を嫌い、コンフリクトが生じないよう意図的にコミュニケーションを疎かにする、という事態になってしまっては本末転倒です。
できれば避けたいコンフリクトですが、「コミュニケーションができているからこその副産物」と考えてみてはどうでしょうか?
コンフリクトはどうしても避けられない故に、メリットやプラスの効果に注目して上手に付き合えるかどうかがポイントです。
■ コンフリクトの原因
- 相性
- 対抗意識
- 予算制約
- 時間的制約
- ストレス許容量
- 戦略、方針の違い
- 初期対応、資源配分の拙さ など
■ コンフリクトによるデメリット、マイナス効果
- 不快感を味わう
- 意思決定に歪みが出る
- 正しい情報が伝わりにくくなる
- しこりが残ると他業務に影響を及ぼす
- 非効率、非生産な作業プロセスが生じる など
■ コンフリクトによるメリット、プラス効果
- 相手の理解が進む
- アイデアを発掘できる
- モチベーションが高まる
- 新たな視点を持つことができる
- 今まで見えなかった問題、課題の発見に繋がる など
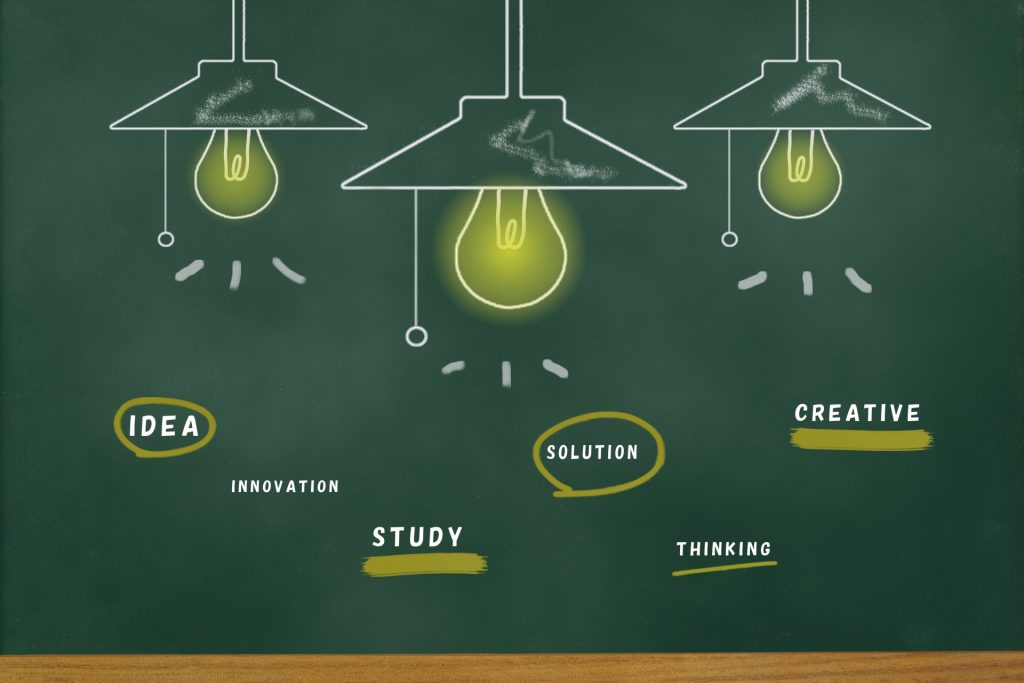
尚、コンフリクトが生じた際の対処方法は3つです。
■ コンフリクトへの対処法
- 交渉する
- 対峙する
- 制御する
コンフリクトの原因、状況を踏まえて、適切な対処を!