会社の成長、規模の拡大、社員数の増加に伴い、組織を設計する、階層を構築する、チームを組成する
【職場づくり|第1回】
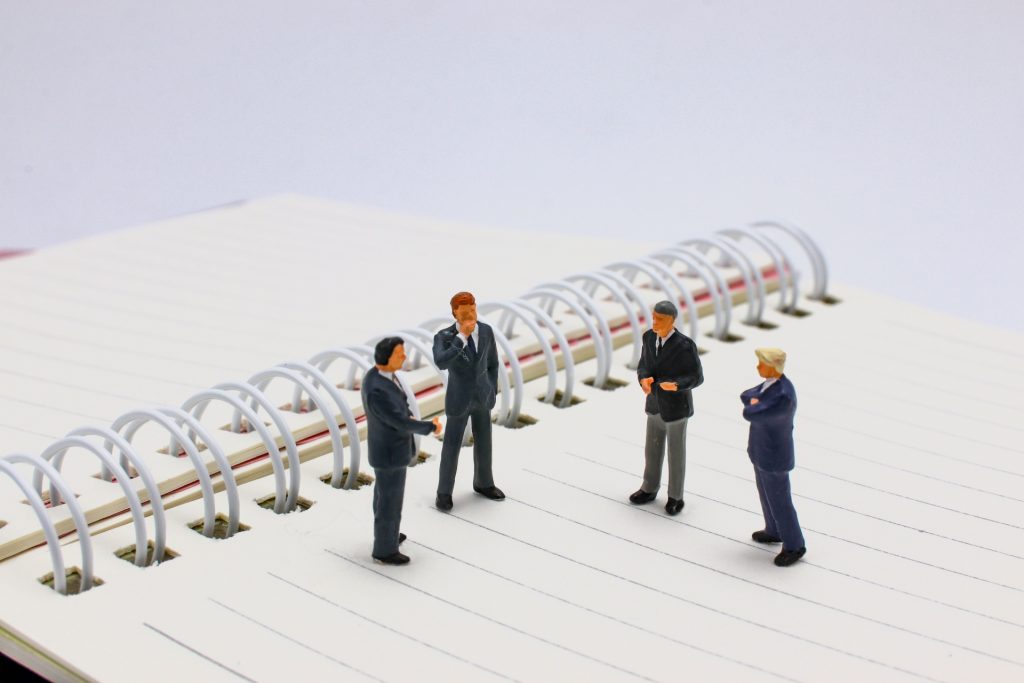
会社の成長フェーズに合わせて、社内の建て付けを整備する
現在活動しているほぼ全ての会社は、成長と拡大を目指して経営しています。成功と失敗を繰り返しながら、徐々に事業基盤を広げて堅固するステップを歩まれているのではないでしょうか。
努力が実を結び、実績が伴うことで、会社は新たなフェーズに入ります。
会社が拡大基調にあるときは、新しい事務所を開設する、新しい商品・サービスを販売する、中途採用を増やす、新卒採用を始めるなど、これまで取り組めなかった施策を次々と実施することができるでしょう。

会社の成長に合わせて、社内の建て付けを見直すタイミングは必ず訪れます。
規模、社員数、業務内容に応じて、最適な建て付けを整備しましょう。予め整備に着手することが一番ですが、何か不具合が起きた場合、一部に業務過多が生じたタイミングには速やかに取り組まれることをお薦めします。
■ 会社を整備する
- 組織を設計する
- 階層を構築する
- チームを組成する
- 権限範囲を規定する
- 役割分担を定義する など
社内を整備する順番や整備の進め方、出来上がりの形に正解はありません。
適材適所の徹底、アメとムチのバランス、働きやすい環境を提供することができれば、社員のモチベーションは向上し、おのずと結果に表れてくるでしょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
組織を設計する
会社を設立した当初は、社員一人ひとりが「いつでも、どこでも、何でも対応すること」が求められます。今いる人員で何事にも対応していかなければ、会社を前に進めていくことはできません。
できないこと、やりたくないことにも前向きに挑戦する人材は、会社の成長フェーズがどこであってもとても貴重な存在です。このような人材には一定の責任と権限を付与して、社内を活性化させるインフルエンサーとしての活躍を期待しましょう。
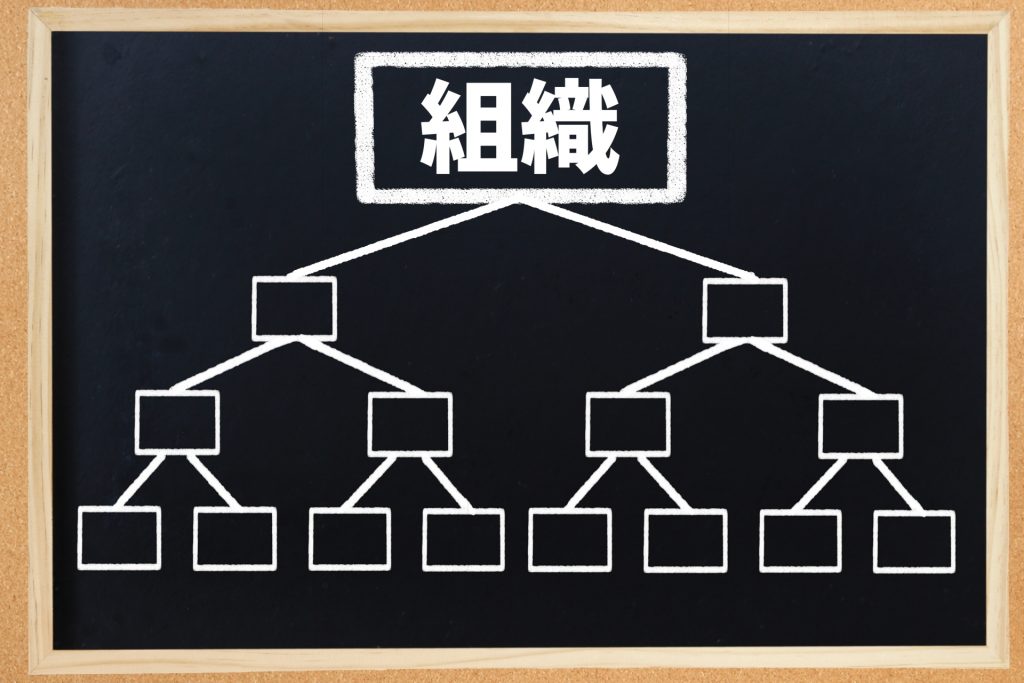
会社の成長に合わせて、対処しなければならない事案は複雑になり、絶対数も増加していきます。専門性が求められるケースも発生し、個人ベースでは対応しきれない状況に陥ってしまう恐れがあります。会社としては組織力で対応できるように、その為の準備を進めなければなりません。
今後発生する可能性が高い事案に適切に対応するためには、どのような組織であるべきか?
人ありきではなく、事案ありき、なりたい将来像をベースにして、組織を設計していきましょう。必要な役割や業務によって部署が生まれ、組織を作り上げていくイメージです。
■ 組織設計の方向性
- より専門的な事案は、組織で対応できるように
- 業務単位ごとに最適なパフォーマンスを発揮できるように
- 責任と権限の範囲を明確にして、組織運営に展開できるように
仕事を作るため、人のポジションを作るために組織を設計することが無いように、注意が必要です。
階層を構築する
会社の成長と拡大に合わせて、中途採用、新卒採用を積極的に行うフェーズに入ります。社員数の増加が階層を作り、人事評価や給与体系の見直し、人材育成や社員教育の取り組みへと繋がっていきます。
今までは経営者、マネージャー、メンバーの3階層であったものが複数の階層に増えるため、上下の距離感が生まれる恐れがあります。ぜひ、このタイミングに社内コミュニケーションのあり方やルールを考えて、何がしかのテコ入れを図りましょう。

尚、一般的に階層は以下のように区分するケースが多い印象です。
それぞれの階層に求めるスキルやスペック、ならびに目標数値や昇格基準は、会社の事情によって設定してください。また、環境の変化や成長フェーズによって、定期的に階層の定義を見直すことをお薦めします。
■ 新入社員
- 学生から社会人となった、入社一年目のビジネスパーソン
- 第二新卒として入社した方も、新入社員として区分されることが一般的
■ 若手社員
- 入社二年目以降で、業務内容を一通り覚えたタイミング
- ビジネスパーソンとしての基礎を備えて、社会人としてのマインドセットは完了
■ 中堅社員
- 専門的な業務を任された上、自分の差配で顧客応対、スケジュール管理ができる
- 目標数値へのコミット、部下や後輩の育成も重要なタスクに
■ マネージャー(管理職)
- 新入社員、若手社員、中堅社員を動かして、チームとして結果を残さなければならない
- 会社への貢献意欲を備えて、モチベーション高く仕事に取り組むことが求められる
■ リーダー
- 責任と権限の範囲が多岐に渡り、組織の浮き沈みはリーダーの双肩に
- 組織としての将来ビジョンと具体化するための道筋を示して、先頭に立って歩む
■ 経営者
- ステークホルダーと対話し、会社全体、グループ全体の最適解を追求する
- 会社を成長、拡大に導く後継者を育成する
チームを組成する

私たちの働き方は、コロナ前とコロナ後で大きく変わりました。人と接することが制限されたことで、テレワークやオンライン化が進み、いつでも、どこでも仕事に取り組める環境になりました。
これまでは「人との関係性」から仕事を依頼される割合は多かったように感じます。しかしながら、これからの仕事は「依頼された期限までに、最適なアウトプットを創り出せる人と仕事をする(仕事が集まる)」という環境に変わると言われています。
■ 今後の仕事のあり方
- アウトプットを創り出すために、社内外から最適なメンバーを集める
- プロジェクト単位でチームを組成し、プロジェクトが終われば解散する
アウトプット重視の働き方になると、アウトプットを創り出せる人材に仕事が集まります。言い換えれば、実績、スキル、ノウハウを備えた上でタイムマネジメントを徹底できなければ、人材として評価されない厳しい環境となるでしょう。
一人ひとりが自分と向き合い、これからどのようにリスキリングしていくか、どのような働き方を目指すのかを考えて、一歩ずつ実績を積み上げていかなければなりません。
自分らしく生きるために、働くためには、相応の努力と自己のブランディングが必要です。

尚、チームを組成する際のポイントの一つは、人数にあると考えています。働きアリの法則にもある通り、2-6-2の割合をチームの組成と運営に反映してみてはいかがでしょうか。
■ 働きアリの法則
- 20% 意欲的に働く
- 60% 普通に働く
- 20% 怠け者になる
この2-6-2の法則は人間にも当てはまる故に、人数が増えればどうしても怠け者が出てきてしまいます。チームを組成する際は、人数と建て付けをコントロールして、出来るだけ怠け者を増やさないようにしましょう。
リーダー研修や管理職研修では、一つの解として「1人+3人」でチームを組成することをご紹介しています。
- 「1人」はリーダーであり、唯一の上位者
- 「3人」はメンバーであり、実際の作業者
メンバーである3名が協力し合い、切磋琢磨する前向きな関係性を構築できれば、効率的にチームを運営していくことができるでしょう。また、この3名がそれぞれリーダーとなり、各リーダーの下に「3名」が連なる構図が作れると、「1+3」の括りを広げていくことができます。
お互いに目の届く範囲で仕事に取り組む距離感は、自身への刺激となり、モチベーションの向上にも繋がります。
最適なアウトプットを創り出すための組織、階層、チームのあり方を、ぜひ考えてみてください。