あれもこれもハラスメント!?適切な距離感、円滑な意思疎通に留意して、ハラスメントが生じない環境に
【メンタルヘルスマネジメント|第3回】
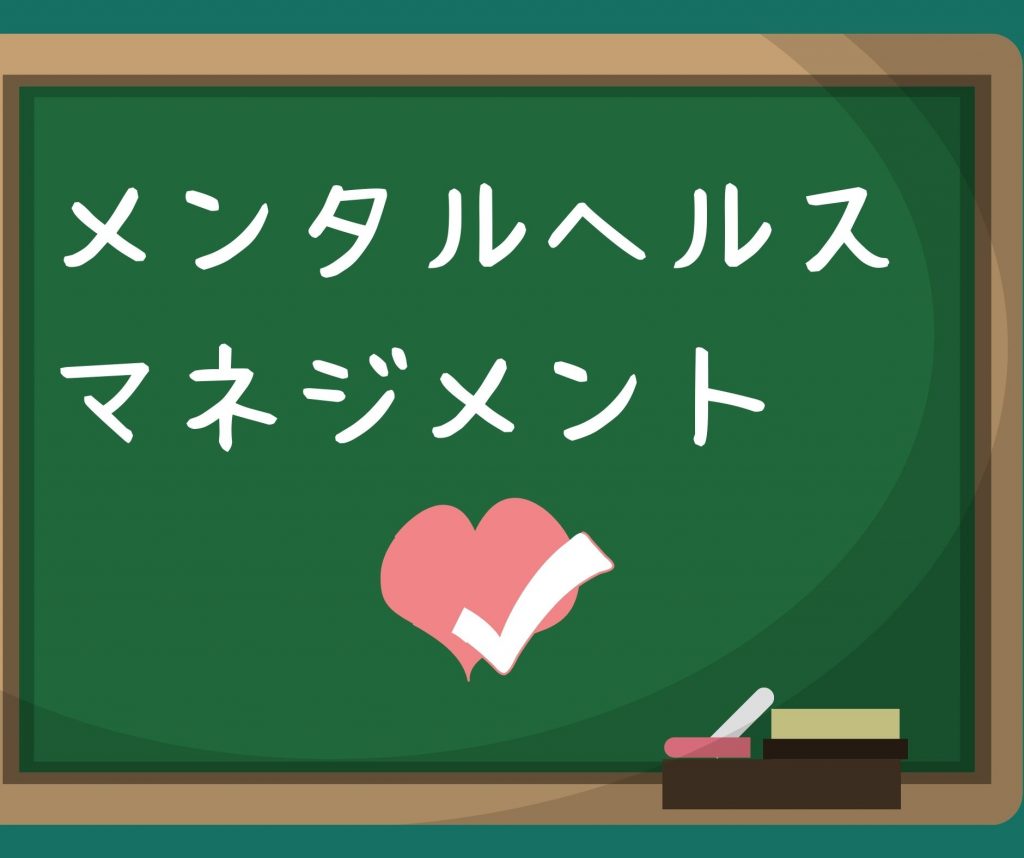
こんなことも、あんなことも、相手の取り方によってはハラスメントになってしまう?!
昨今、メンタルヘルスマネジメント、コンプライアンス遵守をテーマにした研修に取り組む企業が増えてきました。こちらは親切心でも、相手が不快に感じたり、多大なプレッシャーを感じた場合には、それはハラスメントとして認定されてしまいます。
万が一ハラスメントと認定されてしまったら、という恐怖心から、部下や後輩と闊達なコミュニケーションが取れなくなってしまった方は多いのではないでしょうか?
- 自分の世代で流行っていたものは、当然に相手も知っているはず!
- 自分が面白いと思ったものは、当然に相手も面白いと思っているはず!
性別、育った時代、生活していた地域が異なれば、それぞれ異なる情報がインプットされています。自分の持つ情報だけが正である、常識であるという前提で相手と話をしてしまうと、受け手はハラスメントと感じてしまう恐れがあります。
立場の強い側が一方的に話すことはせず、自身の価値観による決め付けをせず、多様性を受け入れる姿勢を取ることができれば、ハラスメントを軽減させることができるでしょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
ハラスメントをしない、させない、許さない職場環境の周知、徹底を
ハラスメントの問題は、メンタルヘルスの不調にも深く関係しています。特にパワーハラスメントについては、しない、させない、許さない職場環境を作れるかどうかがポイントです。
現在、ハラスメントは30種類以上あるとされています。本人は気遣い、心配りであったとしても、意図せずに相手を傷つけてしまう恐れがあるため、相手基準で考える、行動することが求められています。
■ ハラスメントの定義
相手の意に反する行為によって、不快な感情を抱かせること
■ ハラスメントの種類
- パワーハラスメント
- モラルハラスメント
- スメルハラスメント
- セクシャルハラスメント
- アルコールハラスメント
- ジェンダーハラスメント
- ソーシャルハラスメント 他多数

最近では、在宅勤務やリモートワークの浸透、働き方改革の推進により、新たなハラスメントが生まれています。
- 時短ハラスメント 上司や管理職が、部下に対して労働時間の短縮に関する嫌がらせ
- リモートハラスメント 在宅勤務が広がる中で、WEB会議やオンライン飲み会での嫌がらせ
- カスタマーハラスメント 悪質クレーム、消費者による理不尽な嫌がらせ
ハラスメントにならないように、極力関与しない、最低限のコミュニケーションしか取らないという措置を講じる方もいらっしゃいますが、それはそれで「無関心」「マネジメントの不徹底」と評価されてしまいます。
特に、無関心はメンタルヘルスに変調来たす一番の原因です。
相手との距離感をどのように取ることが適切か、相手との信頼関係をどのように構築していくとストレスを軽減できるか、相手に応じてコミュニケーションの取り方を変えられるスキルは、今後更に必要になると思います。
パワハラを見つけた場合は、「見て見ぬ振り」をせずに必ずしかるべき相談先に連絡をして手立てを講じるべし
厚生労働省により、以下の3つの要素を満たすものを職場のパワーハラスメントとして定義しています。
■ パワーハラスメントの定義
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 優越的な地位関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
また、職場のパワーハラスメントに当たりうる行為についても、6つの行為類型を挙げています。
■ パワーハラスメントと見なされる6つの行動
- 人間関係からの切り離し 自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外す、別室に隔離、自宅研修など
- 身体的な攻撃 殴打、足蹴りなど
- 精神的な攻撃 人格を否定するような発言など
- 過大な要求 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命じる
- 過小な要求 社員を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
- 個の侵害 思想や信条を理由として、職場内外で継続的な監視、他の社員に接触しない働きかけ

組織内のポジションが上位になるほど、職場の優位性は高まり、業務の範囲は広がります。故に、そのことを自覚したうえで、自身の権限や業務の範囲を上手にコントロールしながら、組織と人材をマネジメントしていきましょう。
自身の発言や行動は、周りから注目されていることを忘れずに。
また、見て見ぬフリをしてハラスメントを放置することにより、状況の悪化や周囲への悪影響は必至です。
問題を相談しやすい雰囲気、本音で話せる関係性を構築し、人に関心を持って行動するようにしましょう。