プレゼンテーションを特技に!自分の強みと特徴を生かした見せ方、話し方、プレゼンテーションの形を作る
【プレゼンテーション|第2回】
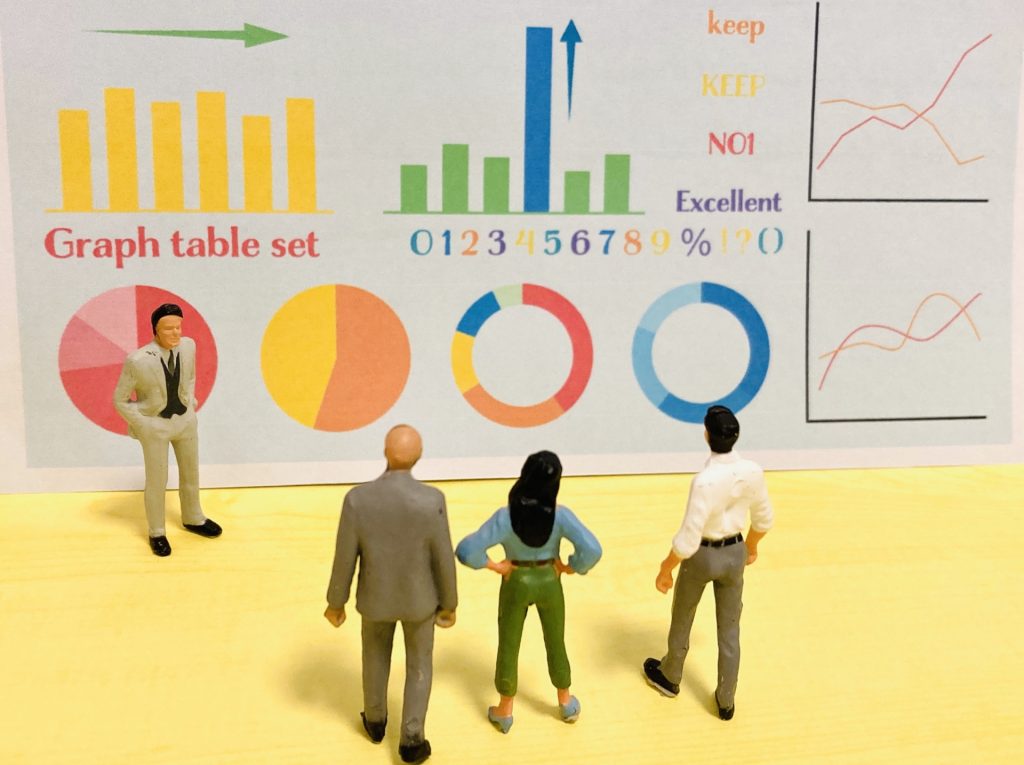
強みを活かして、弱みを補強して、プレゼンテーションに広がりを
普段、私達は無意識に会話をしていますが、自身の話し方、言葉のクセを気にかけたことはありますか?
人それぞれ、話し方には特徴があります。相手が聞き取りやすい、理解しやすい話し方が理想ですが、会話の内容、相手との関係性、その場の環境などをその都度考慮して、最適な伝え方を実践していかなければなりません。
自身の想いを正確に相手に伝えること、相手から目的の言動を引き出すことは、実はとても難しいことです。
「最適な伝え方」を考える前にしておくこと。それは、自身の話し方の特徴を認識することです。自己分析の結果を踏まえて、どういう場面で自身の強みを発揮できるか、どういう場面で自身の弱みが出てしまうのか、今の自身を分析してみましょう。
どんな自分でありたいか、どんな自分を見せたいか、自身の価値観や性格は、そのままクセとしてプレゼンテーションにも表れます。

クセの見つけ方は、2つの軸、4象限を使って行います。
4象限のどれが良い、どれが悪いというものではなく、それぞれに良い面、悪い面があります。相手、内容、時間、環境に合わせて、4象限を使い分けられることが理想です。
- 理性的 ⇔ 感性的
- 言語量多い ⇔ 言語量少ない
■ 話し方のクセの4象限
理性的×言語量多い
- 理路整然、丁寧、くどい、情報過多
- 改善するには、相手に合わせて情報量をコントロールして、聞き手の反応を見ながら緩急を付ける
理性的×言語量少ない
- 合理的、事務的、無味乾燥、遊びが無い
- 改善するには、相手基準で考えて、経験、エピソードなどを織り交ぜながら、明るい雰囲気を作り出す
感性的×言語量多い
- 外向的、明るい、思い付きで話す、脱線気味
- 改善するには、具体例やエピソードは絞り、話の目的を意識して、結論から先に伝える
感性的×言語量少ない
- 内向的、ナイーブ、直感を上手に言語化できない、話が繋がらない
- 改善するには、根拠を明確にして、自分なりのメッセージを順序立てて話す
クッション言葉と豊富なボキャブラリーで、感じの良い伝え方に
話を分かり易く伝えるコツとして、一文を短くして結論を先に伝える、があります。
簡潔に、ハキハキと、分かり易い言葉を使うことで、相手は理解する時間を持つことができます。プレゼンテーションの原稿を作る際は、文章、メッセージをなるべく短く、キャッチーにまとめられるかがポイントです。
但し、短い文章を脈略なく話すだけでは、伝えたいことは正確に伝わりません。文章と文章を繋ぐとき、メッセージを伝えたいとき、雰囲気を変えたいときなどは、クッション言葉を活用すると有意義です。

日頃使っているクッション言葉、いくつ思い浮かびますか?
クッション言葉を入れることで、自身は次の言葉を考える時間を、相手は伝えられた内容を理解する時間を作ることができます。前後の繋がりとタイミングを計りながら、一呼吸置きたいときに取り入れてみてください。
■ 日常で使えるクッション言葉
- 失礼ですが
- お手数ですが
- ご面倒ですが
- 恐れ入りますが
- 差し支えなければ
- 申し上げにくいのですが など
また、相手にメッセージを強調して伝えたい場面では、そのメッセージを同じ意味の言葉に変換し、何度も伝えることで、強いメッセージとして印象付ける手法があります。
■ 「安い」というメッセージを伝えたいときに使える言葉
- 経済的
- お値段以上
- お値打ち価格
- リーズナブル
- 財布に優しい
- セール期間中 など
「安い、安い、安い」と伝えられるより、「お得、経済的、リーズナブル」と伝えられる方が、聞く側のストレスは軽減されるものです。
多くの言葉を吸収してボキャブラリーを充実させることは、プレゼンテーションの上達にも繋がります。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
目的、効果、影響を考慮して、話の組み立てを考える

プレゼンテーションは、テーマ、目的、相手、時間などを踏まえて、どういうストーリー展開が最も効果的かを考えて設計します。情報量が多い場合には、時系列で整理をするなど、聞く側に伝わり易い順番に情報を整理することも重要です。
あくまで相手基準で、より効果が得られる伝え方を考えましょう。
■ プレゼンテーションの代表的な型
起承転結型
- 起 問題提起をして、エピソードを交えて興味を惹く
- 承 現状分析を踏まえて、主題を展開する
- 転 さまざまな視点で、考え方や選択肢を提示する
- 結 ベストな提案をして、全体をまとめる
結承転提型
- 結 趣旨、主張、メッセージを提示する
- 承 前提条件、現状を伝える
- 転 さまざまな視点で、考え方や選択肢を提示する
- 提 結論を詳細に伝えて、提案に繋げる
現状‐問題提起‐解決策型
- 現状 外部環境、内部環境の現状分析を共有する
- 問題提起 見えている問題、見えていない問題を表に出して優先順位を付ける
- 解決策 優先順位の高い問題に対する解決策を提示する
色彩で印象も様変わり!見せ方にもこだわり、ブランディング、安心感に繋げる

色の使い方、見せ方によって、相手が受け取る印象は異なります。服装、資料、照明など、内容に合わせて色を使い分けてみてください。
但し、さまざまな色を多用しすぎると、全体的に重たい印象になってしまいます。また、文字のフォント、ポイントにバラつきがあると、全体的な統一感が欠けてしまいます。
色の使い方、文字の型、文字の大きさを確定させてから、作業に取り掛かるようにしましょう。
■ 暖色系|赤、橙、黄など
- 温かみを持ち、膨張して見えます
- 活動的、パワフル、躍動感、親しみやすさ、陽気、希望などを表現したい場合に活用しましょう
■ 寒色系・無彩色|青、黒、白など
- 落ち着いて、クールに見えます
- 誠実、冷静、知的、強さ、高級感、清潔、純粋、厳粛性を表現したい場合に活用しましょう
■ 中性色|緑、紫など
- 優しく穏やかな印象で、あまり目立ちません
- 安心感、癒し、気品、神秘的、個性的、ナチュラルさを表現したい場合に活用しましょう
本番で成功するための第一声、導入の掴み、目線の置き方
事前にどれだけの準備、練習ができたか、自信はそれに比例して醸成されるものです。自信を持って当日を迎えられるようにすることは、最低限の準備であり、成功への近道と言えます。
その一方で、準備してきたことを本番で存分に発揮できなければ、それまでの苦労が無駄になってしまいます。聞く側の興味を少しでもこちらに向けられるように、プレゼンテーションの入り方には十分に気を配る必要があります。
First impression continues

第一印象はとても重要です。第一印象でこの人の話を聞いてみたい、聞いてみてもよいというイメージを与えることができれば、その後のプレゼンテーションは比較的スムーズに展開できるでしょう。
逆に、悪いイメージを与えてしまった場合には、一生懸命準備してきたさまざまな仕掛けを実施しても、当初のつまずきを挽回することは極めて困難です。それほど、第一印象が人に与える影響は、後々にまで影響を与えてしまいます。
故に、プレゼンテーションの入り方がその後の正否を分けると言っても、過言ではありません。
- 冒頭|全体を見回して、にっこりと笑顔で、大きな声で第一声!
- 掴み|エピソード、質問、データやニュースなどの時事ネタなどを織り交ぜて興味を引き付ける!
- 目線|相手の目を見て話すことが苦手な場合は、目元から口元の範囲を見て話してもOK!
また、「間」を作ることで相手の動きが見えてくることがあります。
静かになる時間はとても怖いですが、話の前後に「間」を入れることで、プレゼンテーションに緩急や緊張感をもたらすことができます。
- 了解を求める間
- 期待を高める間
- 余韻を与える間 など
プレゼンテーションの成功の秘訣は、万全な準備とテクニックを織り交ぜて、プレゼンテーションの締めくくりは感謝を込めて。
「この人はデキる!」と相手に思わせるちょっとしたテクニックも、ぜひ積極的に取り入れてみてください。