金融取引ならびに本業以外の取引は、営業外収益と営業外費用に
【損益計算書|第6回】
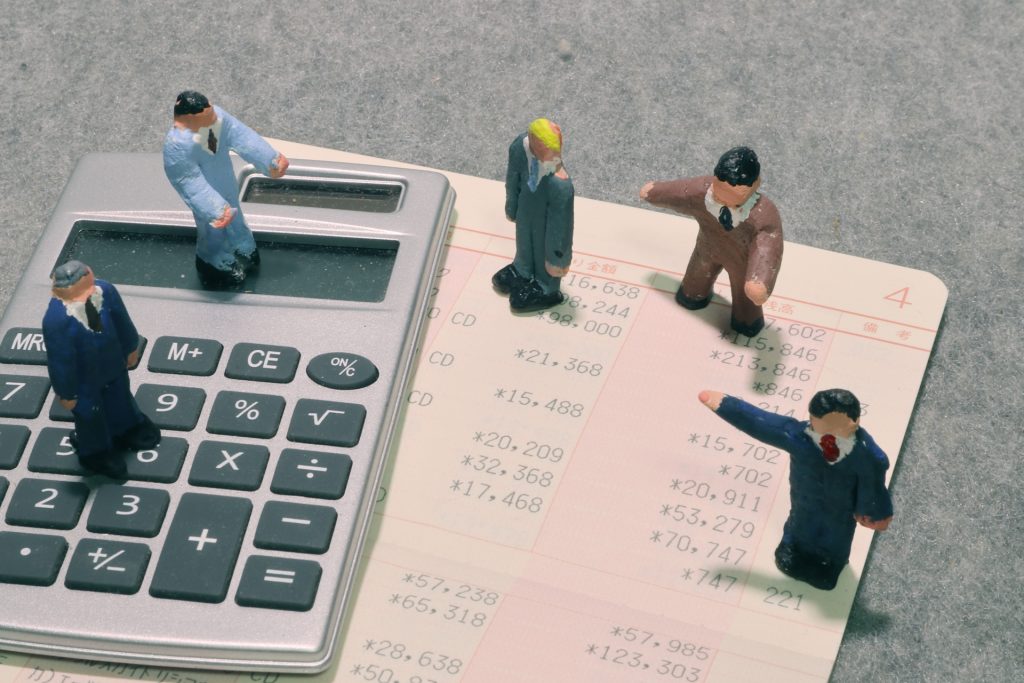
資金の調達や返済、本業以外の取引に関連して発生した入出金は、営業外収益と営業外費用に計上
会社経営や組織運営の際に、商品やサービスの製造、提供以外で発生するお金のやり取りは多くあります。これらは本業の入出金とは分けて、損益計算書の中段に位置する営業外収益、営業外費用として計上されています。
一般社員には関係のない項目が多く(主に経営者や経理担当者が関与する項目)、一社員が日常業務において事細かにチェックすることはないでしょう。但し、資金繰りの良し悪しを知るヒントであるため、経営が悪化している会社ほど注意して見ていく必要があります。
費用より収益が大きければ大きいほど、最終的な利益やキャッシュフローへとつながります。
金額の推移、収益と費用のバランスをチェックして、今後のアクションを検討しましょう!
■ 会計研修のご相談は、ビズハウスへ
本来の営業目的以外から得た収益、金融取引において発生した収益は、営業外収益に

「営業外収益」とは漢字の意味そのままで、営業活動以外で得た収益がこちらに計上されます。端的に、金融取引に関連した収益、資金の運用で得た収益が計上される、と理解すればOKです。
- 金融機関に定期預金として一定の期間お金を預ければ、幾らかの利息が入ってくる
- どこかの会社の株式を購入価格以上で売却すれば、売却益になる
- どこかの会社の株式を保有していれば、配当金を受け取れる など
大多数の企業は、本業とは別に得た金融取引に関する収益を営業外収益として計上しています。
■ 営業外収益の細目
- 受取利息
- 受取配当金
- 有価証券利息
- 受取家賃
- 受取地代
- 雑収入 など
尚、営業外収益の細目に受取家賃と受取地代があります。これは、保有する不動産を第三者に賃貸したことで得た賃貸収入を表します。
不動産賃貸が本業であれば、受取家賃や受取地代は売上高として計上されます。一方、本業が別である場合には、これらは営業外収益として計上されるのが会計のルールです。
これまでに多くの決算書を拝見してきましたが、受取家賃、受取地代を計上している会社はそこそこ多い印象です。何かをきっかけに不動産を保有しているケース、余剰資金を不動産に投資しているケースは多いのではないでしょうか。
■ 預金と貯金の違いとは?!
- 預金 銀行、信用金庫などにお金を預けること ※利息が入る
- 貯金 ゆうちょ銀行、農協、漁協でお金を貯めること ※利子が入る
本来の営業目的以外から発生した費用、金融取引において発生した費用は、営業外費用に

こちらも漢字の意味そのままで、営業活動以外で発生した費用、ならびに金融取引に関連した費用が計上されています。特に、資金調達及び返済に関連して発生した費用、と理解すればOKです。
■ 営業外費用の細目
- 支払利息
- 社債利息
- 手形売却損
- 有価証券売却損
- 雑支出 など
営業外収益と営業外費用を比較して、営業外収益の方が大きいケースがあります。これは潤沢な資金を上手に運用できており、借入金の返済が少ない状況にあることが推測できます。
よって、営業利益より経常利益が大きい会社は、「資金繰りに問題無し」と評価してOKでしょう。
手元のキャッシュフローは手厚く、と考えるのが企業経営の鉄則であり、それが実現できれば営業外収益は大きくなっていく構図です。
【アーカイブ|損益計算書】
- 1|売上高 企業規模が分かる、業績の好不調が分かる
- 2|売上原価 自社の商材を提供できるカタチにするまでにかかったコスト
- 3|売上総利益 商品・サービスの力や付加価値が分かる
- 4|販売費及び一般管理費 経営や組織運営に関するほぼすべてのコスト
- 5|営業利益 事業・ビジネスモデルの力が分かる
- 7|経常利益 金融取引を含めた会社全体の力が分かる
- 8|当期純利益 株主還元と将来への投資の原資