最善、最適な言動を導き出す!フレームワークを活用して、情報やデータから示唆を得る、裏付けを取る
【情報活用|第2回】

収集した情報やデータの整理と分析は、フレームワークを活用して
さまざまなデータソースから収集した情報やデータは、手元にあるだけでは宝の持ち腐れです。外部環境や内部環境を、数字と言葉の両面から比較、分析して、目的の示唆、裏付けを得ていきましょう。
尚、分析に使えるフレームワークはさまざまあるため、目的に応じてどれが最適かを判断しなければなりません。
多くのフレームワークを活用することがいいという訳ではなく、現状を整理して「欲しい解」が得られるように、情報やデータの客観性、納得性、権威性に留意してフレームワークに落とし込みましょう。
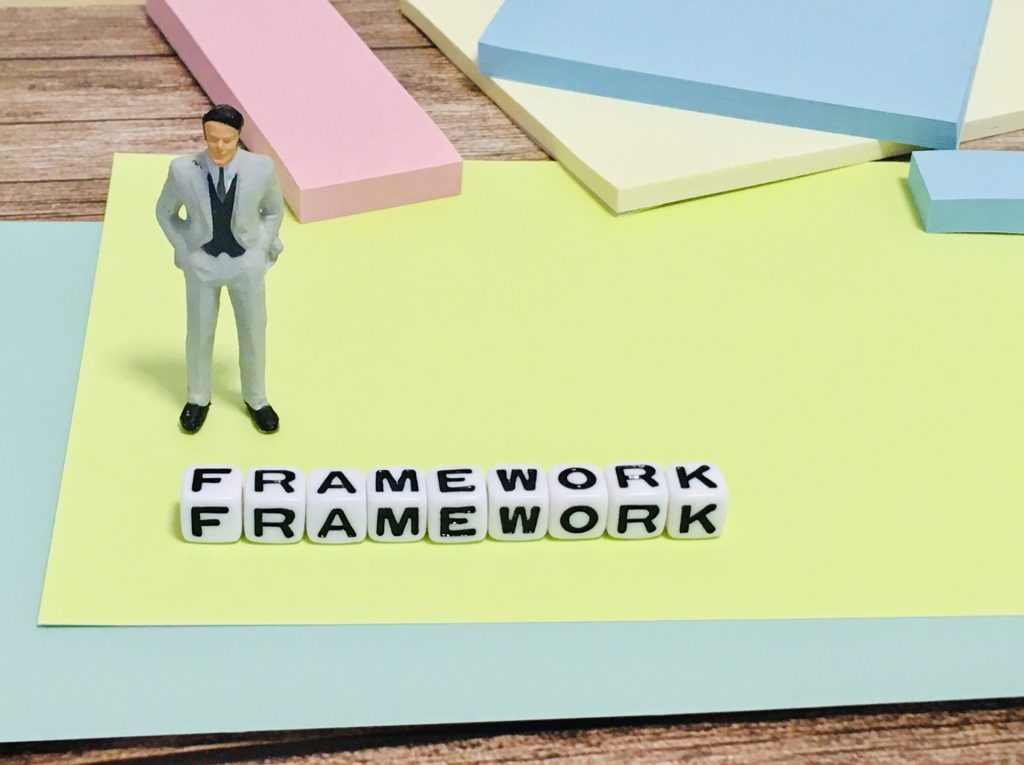
一般的によく使われているフレームワークを、以下ご紹介します。
全国平均やベンチマークとの比較、過去から現在までの推移を見ながら、現状の良し悪しを把握してみましょう。
■ 分析フレームワークのご紹介
- PEST分析|周りを取り巻く環境を、政治、経済、社会、技術の4つの要因から分析する
- 7つの資源|ヒト、モノ、カネ、情報、時間、知的財産、モチベーションの7つの資源から内部環境を分析する
- SWOT分析|内部の環境や資源を強みと弱みに、外部環境の変化を機会と脅威に分類して分析する
- ポジショニングマップ|独立した2軸を使って全体構図と現在の位置付けを把握して、独自で優位なポジションを探す
- 7S|3つのハード(構造、戦略、システム)、4つのソフト(能力、文化、人材、価値観)の視点で分析する
- 損益分岐点|固定費、変動費、限界利益、損益分岐点売上高・比率を用いて、現状を定量的に分析する
示唆を得る、裏付けを取るために求められるスキルや考え方は異なる
分析結果をもとに、将来への示唆や方向性、裏付けを導き出すのが次の作業です。何のための分析か、分析結果から何が欲しいのかによって、求められるスキルは異なってきます。
示唆が欲しいとき、裏付けが欲しいときに必要とされるスキルや考え方は、以下のように定義できるのではないかと考えています。分析だけで終わらずに価値あるアウトプットを出せるかどうかが、ビジネスパーソンとしての腕の見せどころと言えるでしょう。
■ 示唆が欲しいときに求められるもの
- 想像力
- 思考力
- 経験
- 閃き など
示唆が欲しいときは、現状分析の結果や最新情報をもとに閃きに繋げていきます。身近な声、少数意見、関係者以外の声など、広い意見を採用するほど有意義な示唆を導き出すことができるでしょう。
但し、示唆が得られるタイミングはいつになるかは分かりません。また、人によって導き出した示唆は異なるため、チーム内で認識を一致させる作業が必要になります。
■ 裏付けが欲しいときに求められるもの
- 客観性
- 論理性
- 正確性
- 権威性 など
裏付けが欲しいときは、導き出した結論や方向性に信頼性と権威付けをどれだけできるかがポイントです。情報の質と量、データソースの信頼性、定性情報と定量情報を組み合わせなど、受け手の納得感が得られる構成を考えなければなりません。
上記のほかにも、示唆が欲しい、裏付けが欲しいときに求められる要素はあると思います。足りない要素、必要な要素があれば、リスキリングを通じて強化していきましょう。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
目的を実現するために、示唆や裏付けを踏まえた最適な行動を

示唆や裏付けが得られたら、あるべき姿、将来ビジョンの実現に向けて実際の行動に移りましょう。
行動計画の策定は、3つの切り口で組み立てていくことをお薦めしています。全体像を固めてから、細目を詰めていくイメージです。
■ 何を動かすか?
自分は頭を動かす立場か、体を動かす立場か、テーマごとの期待役割を理解しましょう。また、どのくらいの資源を準備できるか、手元の資源をどのように動かすのが効果的かを組み立てていきましょう。
- 頭を動かす
- 体を動かす
- ヒトを動かす
- モノを動かす
- カネを動かす など
■ どちらを向くか?
何をターゲットに、どこにメッセージを発信するか、年齢、地域、所得などに整理してアプローチ先を選定しましょう。強みを活かすのか、弱みを補うのか、その方向性も明確に。
■ 流れに伸るか反るか?
世の中の文化やトレンドには流れがあります。追い風に便乗するか、独自のスタイルを貫くかは、その時々の方針によって左右されます。成長、拡大に繋がる道筋はどちらか、経営者には冷静な判断が求められています。
分析結果から得られた示唆や裏付けが正しいかどうかは、誰にも分かりません。但し、何かを判断する際には材料が必要で、失敗しないためには事前のインプットは必須です。
最適な行動に繋げるために、そして確実に結果を残せるように、情報の活かし方をブラッシュアップしていきましょう。
相手に何を伝えるかによって、情報・データの見せ方に一工夫を!

手元の情報や分析結果を正確に伝えるには、言葉に加えて、グラフや数字を使った視覚による訴えも非常に効果的です。
グラフは、パッと見たときに傾きが大きいほど、その影響や効果は大きいと理解する(錯覚する)傾向にあります。インパクトを大きく(または小さく)見せたいかによって、タテ軸とヨコ軸の取り方、メモリの刻み方を調整してください。
また、数字については、表現の仕方はさまざまです。
■ 数字の見せ方
- 平均値
- 最大値
- 最小値
- 成長率
- 伸び率 など
対象期間をどこで区切るかによって、導き出される結果は大きく異なります。
期間の区切りを恣意的に出来る故に、レンジで見せたり、移り変わりを見せたり、インパクトのある数字が出てくる期間を採用しましょう。情報を加工する側は見せ方に注意を、情報を見る側は本質を読み解けるように。