資金調達は、負債の部と純資産の部で詳細を確認!低コストで調達する手段、組み合わせを考える
【貸借対照表|第3回】
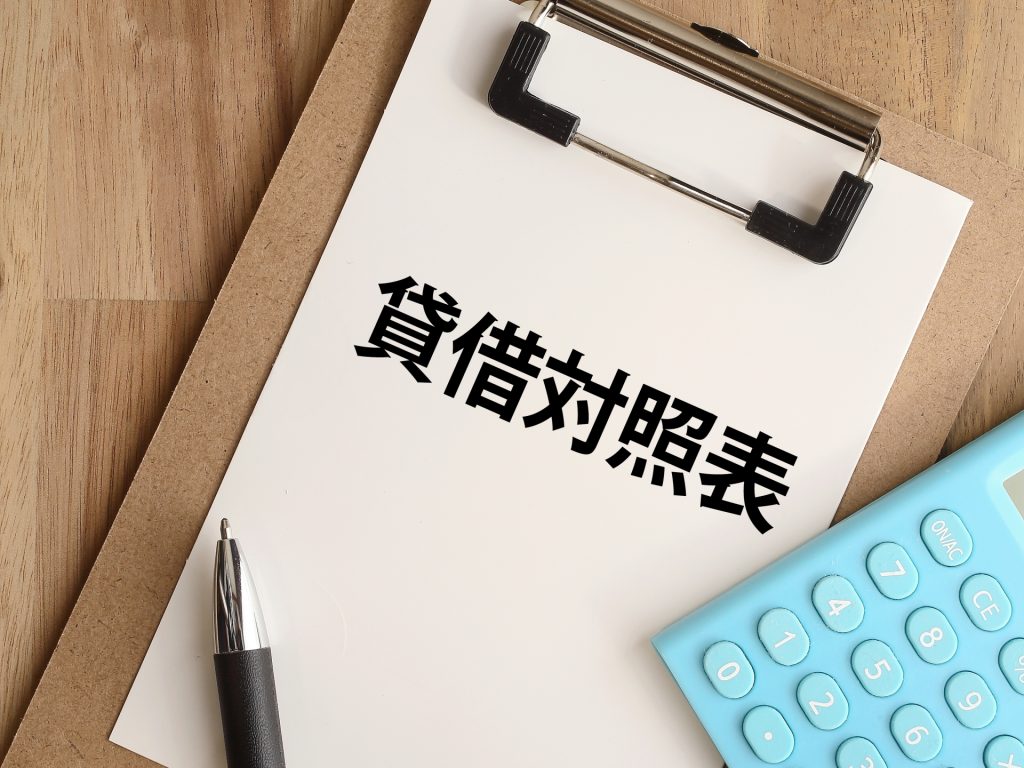
貸借対照表の負債の部は、流動負債と固定負債で構成される
貸借対照表の右側には、過去のある一時点において、どこからいくら調達したのかが一覧になって掲載されています。上段は負債の部、下段は純資産の部となっており、負債の部は流動負債と固定負債の2つの枠組みで構成されています。
流動負債には、一年以内に支払わなければならない負債(借金や費用など)、ならびに一年以内の出費への備え(引当金)が入ります。一方の固定負債には、一年を超えて支払わなければならない負債、ならびに中長期的な将来の出費への備えが入ります。
流動負債と固定負債の境界ラインは「一年以内に支払う必要があるかどうか」で、資産の部と同様に、一年が判断の基準になります。
■ 代表的な流動負債
- 買掛金|取引先から購入した代金のうち、まだ支払っていない金銭
- 前受金|商品の販売引き渡しや、役務の提供が完了する前に受け取った金銭
- 未払費用|すでに提供されている役務に対して、対価の支払いを終えていない金銭
- 短期借入金|決算日以後、1年以内に返済期限が到来する金銭
- 賞与引当金|翌期に支給するボーナスに備えて、見積もり計上するもの など
■ 代表的な固定負債
- 社債|設備投資などの事業資金を調達するために発行する債券
- 長期借入金|決算日の翌日から1年を超えて返済する予定がある金銭
- 預り保証金|契約に従って、一定期間サービスや権利を提供するために受け取った金銭
- 退職給付引当金|将来支払われる退職金のうち、現在までに発生している分を見積もり計上するもの など
日常業務や短期的な資金繰りへの対応は、流動負債で調達するのが一般的です。一方、M&A、設備投資、新規事業開発など中長期的な施策への対応は、固定資産で調達することが推奨されています。
お金に色はありませんが、資金の調達期間(コストを負担する期間)と運用期間(リターンが得られる期間)を合わせることで、会社全体の資金繰りを安定させることができるでしょう。
■ 会計研修のご相談は、ビズハウスへ
資金調達手段はさまざま!必要な資金を、低コストで調達する手段と組み合わせを考える

会社はお金が無ければ始めること、続けることはできません。資金調達や資金繰りのチェックは、会社の命運を握る重要な業務であり、経営者にとっては大きなプレッシャーとなっています。
一昔前は「金融機関からの融資」が代表的な資金調達でしたが、現在はさまざまな手段が用いられています。必要な資金をより低コストで調達するための手段や組み合わせを選択できる環境は、会社側にとって有利な状況にあるのではないでしょうか。
まさに財務部の腕の見せどころ!
日常からのコミュニケーションや新しい手段を取り入れるなど、自社にとって最適な資金調達を取り組んでいきましょう。
■ 資金の出し手、調達の手段は多様化
- 銀行
- 信用金庫
- ファンド
- ベンチャーキャピタル
- クラウドファンディング など
純資産は、株主からの出資と毎年の利益の積み重ねで構成される

大企業の純資産の部を見てみると、何だか小難しい勘定科目が並んでいます。但し、これらがすべての企業に掲載されている訳では無いので、純資産を構成する要素は大きく2つ、と理解しておけばOKです。
■ 純資産を構成する2つの要素
- 株主からの出資
- 毎年の利益の積み重ね
株主からの出資は、資本金と呼ばれるものです。増資をした場合、株主からの出資金のうち最低でも1/2以上は資本金に、残りは資本準備金として計上することがルールになっています。
毎年の利益の積み重ねとは、損益計算書の最下段「当期純利益」の一部の金額が、利益剰余金という名目で純資産に計上されることを表します。言い換えれば、会社が生み出した利益を積み立てた結果であり、会社内部に蓄積されたものを指します。
よって、業績が良く、利益が増えれば利益剰余金も順調に増えていきますが、赤字が続いた場合には利益剰余金は減少していきます。
利益剰余金がマイナスの会社は、厳しい経営状況が続いていると評価してください。