リアクションはオーバーに!意見や主張はハッキリ伝えて、アサーティブな関係に
【コミュニケーション|第4回】

コミュニケーションはキャッチボール!聞く姿勢、耳を傾ける態度は、円滑なやり取りに大切な要素です
他人と分け隔てなくやり取りする関係、コミュニケーションを求められると、どのように発信するかに意識が偏ってしまう方は多いのではないでしょうか。誰に対して、何を発信できるのかを第一に考えて、実践されている方が大多数ではないかと思います。
何がしかを発信することがコミュニケーションのスタートである故、発信力も重要な要素であることに間違いはありません。
しかしながら、コミュニケーションは行ったり来たりのキャッチボールで成立することを踏まえれば、相手の発信を受信する力、つまり、「聞く姿勢」「耳を傾ける態度」も重要な要素の一つと考えなければなりません。
双方が自分の言いたいことを言い合っているだけでは、建設的な議論になりません。相手の発信を踏まえた回答を積み重ねていけるかどうかで、コミュニケーションの濃淡が決まります。
日頃から相手の話を聞く姿勢、耳を傾ける態度はできているか、自己評価してみましょう。
■ どちらの相手が話しやすい!?
- こちらが提供する話題に関係なく、自分が話したいことを話してばかりな相手
- こちらが提供する話題に耳を傾け、内容をしっかりと理解した上で、自分の意見や感想を返してくる相手

コミュニケーションは聞き手の動きが成否を分ける、と言っても過言ではありません。
聞き手の姿勢や態度によって、話し手は気持ちよく話せたり、話し辛さを感じます。また、時間を短く感じることもあれば、長く感じることもあるでしょう。
人は自分の話をしたい、という欲求を持っていると仮定すれば、相手の話を聞くことは、相手を受け入れていると先方に感じてもらえる効果があると考えてみましょう。親身に聞く姿勢は相手に伝わり、相手からは親身に聞く姿勢を引き出すことができるでしょう。
鋭い質問、研ぎ澄ました意見を連発していては、相手は引いてしまいます。
相手に話させるスタンスで、コミュニケーションは十分に成立します。
■ 研修のご相談は、ビズハウスへ
時にオーバーなリアクションも!相手の本音を引き出すために、3つの動作を組み合わせる
自分の本音は、どのような場面やタイミングで表に出すことができますか?
相手や内容によって、本音を話せるまでにかかる時間は異なるのではないでしょうか。
また、相手が聞く姿勢の状態に無ければ、自分の本音を話したいとは思えません。言い換えれば、聞き手が聞く姿勢の準備ができていなければ、どれだけ時間が経っても本音を話すことはないということです。
話し手に対して聞き手は体全体でアピールし、表現することがポイントです。体全体、顔の表情、視線の3つの動作を組み合わせて、相手から本音を引き出していきましょう。
■ 体全体でアピール
- 大きく頷く
- 相槌を入れる
- 身を乗り出す
- 腕組みをしない
■ 表情でアピール
- 悩みを聞いてるときは、同情的な表情で
- 楽しい話をするときは、笑顔で
- 内容によって、表情を変える
■ 視線でアピール
- 暖かい眼差し
- 目線を合わせる
- 適度に視線を外す
- 視線を泳がせない

先に相手の情報をインプットした方が、その後の行動を効率的に進めていくことができるようになります。例えば、相手の状況やニーズに対してピンポイントの商品提案やフォローができれば、余計な提案書の作成、質疑を何度もやり取りする必要はありません。
先に情報を引き出した方が、自分にとって有利な展開に持っていくことができると考えてみましょう。
聞く姿勢、耳を傾ける態度を日常的にできるようになれば、自然と人が集まるようになります。人が集まれば情報が集まり、結果的には自分にとって大きなメリットを手にすることができるでしょう。
- 上司や先輩からは、話せる後輩に!
- 部下や後輩からは、相談できる先輩に!
聞く力を向上させて、自分の存在価値を高めていきましょう。
コンフリクトを恐れず!プラス効果に注目して、意見や主張はハッキリと伝える関係性に
コミュニケーションを円滑に行えるようになると、意見や主張の食い違い、対立、軋轢(コンフリクト)が生じる事態が増えてきます。これらはコミュニケーションが取れている証拠であり、コンフリクトを避けるためにコミュニケーションを疎かにしては本末転倒です。
コンフリクトにも、プラスの効果があります。コンフリクトは起きることを前提に、原因を突き止めて解決する、プラス効果に注目して上手に対処していけるようになれば、組織マネジメントのキーマンとして評価されるようになるでしょう。
■ コンフリクトのプラス効果
- アイデアをブラッシュアップできる
- 見方や考え方を明確にできる
- 相手への理解が進む など
■ コンフリクトのマイナス効果
- 不快感を味わう
- 正しい情報が伝わらない
- しこりが残ると他業務に影響が出る など
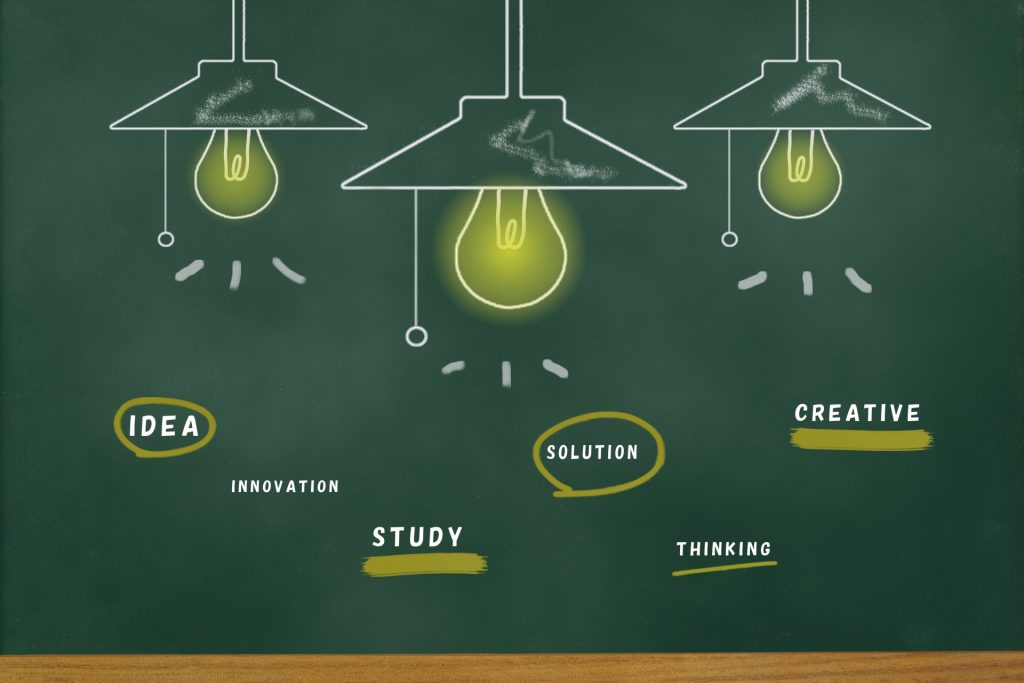
尚、コンフリクトが生じる原因は、送り手と受け手(話し手と聞き手)の双方にあります。
送り手の問題は、受け手に好印象を持ってもらいたいために、送り手が情報を操作してしまうことが挙げられます。情報をコントロールして優位性を確保することは「情報の非対称性」を生み出し、後々の火種となる恐れがあります。
一方、受け手の問題は、自分の関心や期待によって、物事を都合よく解釈してしまうことが挙げられます。特定の情報、偏った理解による言動は、ときに周囲が受け入れられない状況を生み出してしまう恐れがあります。
その他にも、文化、習慣、年齢、階層、立場、業務の違いによって、言葉や動作の意味は異なります。
相手の立場を考慮してコミュニケーションが取れるように、お互いがリスペクトし合える関係性を構築していきましょう。
【アーカイブ|コミュニケーション】
- 1 頭と体を動かして最適なアウトプットを提供できるように
- 2 目的、相手、タイミングに応じて、最適なコミュニケーションを模索する
- 3 知性、信頼、親しみやすさを表現して、相手に受け入れてもらう準備を
- 5 意見しやすい雰囲気、意見を言う甲斐が、コミュニケーションを活性化させる