より現金に近い資産であるほど上部に掲載!流動資産、固定資産の定義と枠組みを理解する
【貸借対照表|第2回】
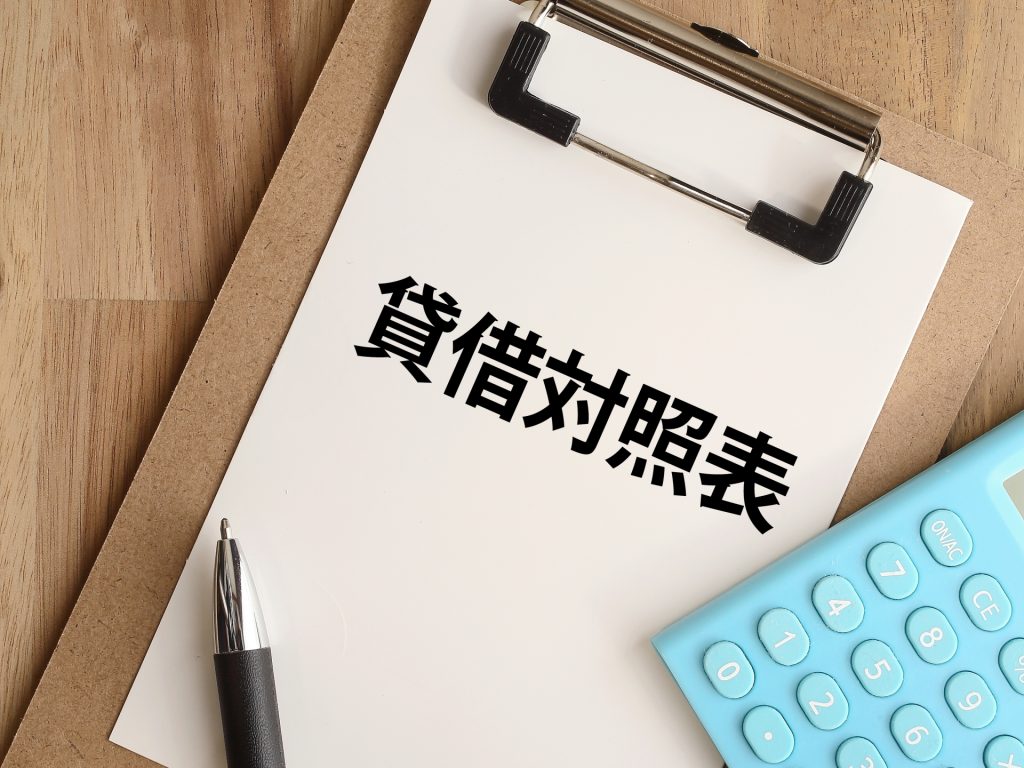
貸借対照表の資産の部は、流動資産と固定資産で構成される
過去のある一時点において、会社が保有する資産が一覧になって掲載された資料のことを貸借対照表(資産の部)と言います。形があるモノもあれば、形が無いモノもあり、一定のルールに基づいて掲載されています。
尚、貸借対照表の資産の部は、流動資産と固定資産、大きくこの2つの枠組みで構成されています。
流動資産には、一年以内に現金化することができる資産が入ります。一方の固定資産には、一年以内に現金化することができない資産、ならびに一年を超えて保有する(そもそも現金化する予定がない)資産が入ります。
以上から、流動資産と固定資産の境界ラインは「一年以内に現金化できるかどうか」であることが分かります。
より現金に近い資産(流動性の高い資産)であるほど、資産の部の上部に掲載される(流動性配列法)のもルールの一つです。
■ 会計研修のご相談は、ビズハウスへ
会社の資金繰りは、流動資産で要チェック

前述の通り、会社が保有する資産のうち、一年以内に現金化できる(現金化したい)資産が入る枠組みが流動資産です。
実際に保有する資産が順番に掲載されるのが一般的ですが、上場しているような大企業の場合、更に3つの枠組みで構成されています。
■ 流動資産を構成する3つの枠組み
- 当座資産|現金に最も近い資産が入る
- 棚卸資産|部品や仕掛品など、商品在庫が入る
- その他流動資産|上記以外の資産が入る
当座資産は、流動資産の中でもより現金に近い資産が入る枠組みです。手元の現金や預金は勿論のこと、売掛金、受取手形、未収入金、短期貸付金などが入ります。
棚卸資産は、自社の商品やサービスに関する在庫が入る枠組みです。仕入れた材料、製造中の商材を対象に、原材料、仕掛品、貯蔵品、半製品などの名称で入ります。また、未だに販売できていない商材についても、商品、製品などの名称で入っています。
その他流動資産は、上記に入らなかった資産が入る枠組みです。先に支払い済みのものや、勘定科目が不明なものを一時的に計上するなど、さまざまな資産が入っています。
- 前渡金|仕入れの際の手付金
- 仮払金|勘定科目が不明なものを一時的に計上
- 前払費用|来期にサービス提供を受けるものを先払い など
モノへの投資は、固定資産に計上される

会社が保有する資産のうち、中長期的に使用する資産、ならびに一年以内に現金化できない資産が入る枠組みが固定資産です。
流動資産と同様に、固定資産の中も3つの枠組みで構成されているケースがあります。
■ 固定資産を構成する3つの枠組み
- 有形固定資産|形があり、手に取れる資産が入る
- 無形固定資産|形が無く、目に見えない資産が入る
- 投資その他の資産|上記以外の資産が入る
有形固定資産は、その名の通り「形が有る資産」が入る枠組みです。土地、建物、機械及び装置、車両など、資産として認識しやすい形のあるモノは、ほぼこちらの枠組みに入っています。
無形固定資産は、主に権利に関連する資産が入る枠組みです。特許権、商標権、意匠権、電話加入権、M&Aの際に生じるのれん代などが、こちらの枠組みに入っています。
投資その他の資産は、上記に入らなかった資産が入る枠組みです。主に保有する株式(グループ内企業)や保険積立金、長期貸付金などが入っています。
保有する資産が資金調達の担保に入っているケースに要注意!

企業を成長、拡大させていくには、元手となる資金が必要です。その際には、金融機関から融資を受けるケースが一般的です。
但し、いわゆる裸与信で融資を受けられるのは一部の企業のみ。取引実績があり、絶好調の企業以外は、何がしかの担保を提供して資金調達しているのが実態です。(または、保証協会の保証枠内で資金調達しています)
土地、建物、株式、保証金など資金調達の担保に提供した資産に対して、資金の出し手は権利を設定します。返済が窮した場合に資産を現金化し、優先的に返済が受けられる内容になっています。
以下の3種類のうち、資産内容に応じて担保を設定します。
- 質権|不動産以外の資産が対象
- 抵当権|主に不動産が対象で、債務者は継続して不動産を使用することができる
- 根抵当権|限度額を定めて担保を設定し、繰り返し金融機関との取引ができる
担保を設定された資産が多い場合には、貸借対照表の数字を額面通りに受け取ることはできません。
幾らの権利を設定されているのか、保有する資産を個別にチェックして確認していく必要があります。