貸借対照表は5つのハコで構成された調達と運用の一覧表!どこからお金を調達して、何に使い、何を持っているかが一目瞭然!
【貸借対照表|第1回】
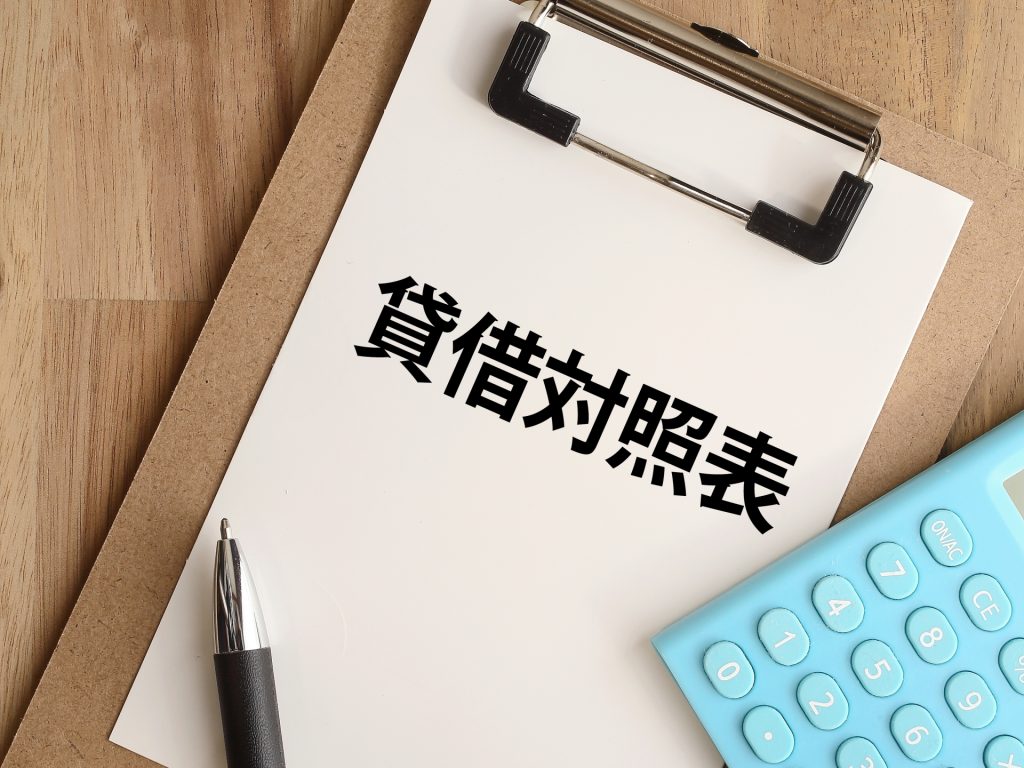
経営状況は財務三表でチェック!会社全体の財務状況の確認は貸借対照表で
企業経営や組織運営においては、毎日さまざまな取引や活動が行われています。会社の規模が大きく、社員数が多数であればあるほど、膨大なお金のやり取りが発生しています。
経営者はそれらを最適にマネジメントすることが重要なミッションであり、目標の実現を目指すべく相応のエネルギーを費やしています。
決算書とは、一年間の企業活動の結果が数値として掲載された資料です。3種類で構成されており、財務三表とも呼ばれています。
■ 財務三表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
貸借対照表はその一つで、ある一時点における資金調達、ならびに資金運用の細目が一覧になって掲載されています。
調達の合計額(貸借対照表の右側)と運用の合計額(貸借対照表の左側)は、古今東西、大企業から中小企業まで、世界中のどの企業も左右の金額は必ず同額です。左右の金額はイコール(≒バランス)であることから、バランスシートと呼ばれています。
尚、貸借対照表を「BS」と表記しますが、これはバランスシートの英語表記(Balance Sheet)の頭文字から命名されたものです。
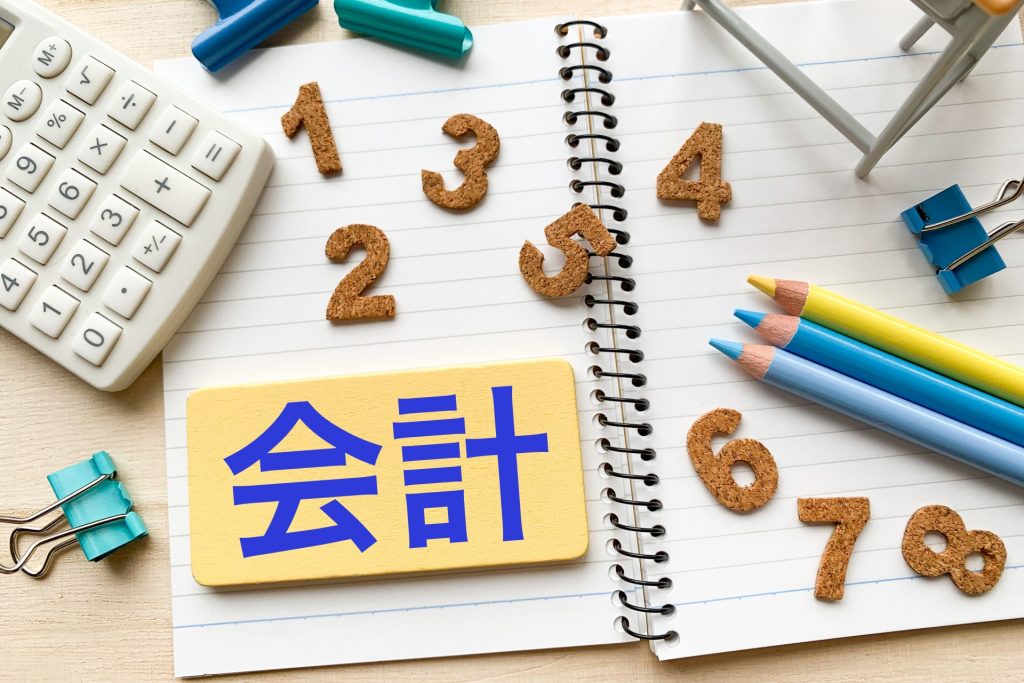
財務三表のうち何を重視するか、充実させるかは、企業によって方針は異なります。商材、ビジネスモデル、市場規模や他社との競争状況などを考慮して、その時々の経営者が最適な判断をしなければなりません。
一般的に、重厚長大なインフラが無ければ商品・サービスを提供できない企業や業界は、貸借対照表を重視する傾向にあります。
電力、ガス、鉄道、航空などが代表格で、充実した資産がより大きな価値を生み出すとされているため、保有資産の入れ替えや最新化には積極的に取り組んでいます。
貸借対照表は5つのハコで構成!それぞれの定義を理解して、良し悪しを判断できるように
貸借対照表は、5つのハコで構成されています。
大企業から中小企業までこの骨格は変わらないため、まずは5つのハコの定義を理解することが肝要です。

■ 資金運用側のハコ
- 流動資産
- 固定資産
流動資産とは、一年以内に現金化できる資産が入るハコ(枠組み)です。一方の固定資産は、一年以内に現金化できない資産、ならびに一年を超えて保有する資産(そもそも現金化する予定がない資産)が入るハコになります。
流動と固定の境界は、一年以内に現金化できるか否かです。
流動性の高い資産であるほど、上部に掲載されるルール(流動性配列法)に基づいて作成されています。
■ 資金調達側のハコ
- 流動負債
- 固定負債
- 純資産
流動負債とは、一年以内に返済しなければならない負債、ならびに支払わなければならない費用が入るハコです。一方の固定負債は、一年を超えて返済していく負債が入るハコになります。
こちらも流動と固定の境界は一年で、出金するまでの時間が短いほど上部に掲載されます。
純資産とは、株主からの出資、ならびに毎年の利益の積み上げにて構成されていると理解できれば、大枠はOKです。株主からの出資は資本金、資本剰余金へ。毎年の当期純利益の一部(または、当期純損失)が、利益剰余金に反映される仕組みになっています。
貸借対照表の分析は、これら5つのハコを活用します。
ハコとハコを比較してどちらが大きいか、全体の中で該当するハコは何割を占めるかなどで、良し悪しを判断していきます。
■ 会計研修のご相談は、ビズハウスへ
使ったお金は投資か、消費か?!使い方や使い道によって、掲載される場所は異なる

企業活動、そして一人ひとりの仕事の種類は多岐に渡ります。入金に繋がる業務もあれば、出金に繋がる業務もあり、社内にいる人材を適材適所に配置して、責任、権限、役割を分担して取り組んでいます。
原則、入金は売上に関係する活動であり、その他の活動は出金に繋がります。出金も投資と消費の2種類あり、使い方によって出金額が掲載される場所は異なってきます。
■ さまざまな企業活動
- 採用/育成
- 仕入/製造
- 営業/販売
- 投資/研究開発
- 返済
- 納税 など
投資とは、未来に向けた取り組みであり、その恩恵は時間が経ってから得られるものです。そのため、投資金額は何がしかの形で資産となり、貸借対照表に計上されるのが一般的です。
M&Aを例に挙げると、買収資金は有価証券(及び、のれん代)に項目を変えて、貸借対照表に掲載されます。
投資は貸借対照表へ、消費は損益計算書へと覚えておくと、分かり易く理解できると思います。